|
|
 |
 |
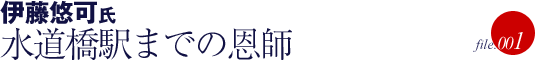 |
 |
 宝生能楽堂の玄関を出ると、すでに陽は西に移っていて老若の客が帰途を急いでいた。舞台にひたった昂りを鎮めてくれる夕風は心地よかった。私は上着のポケットから煙草を取り出しくゆらせていたのだが、ふと上品な小柄の老婦人が寄って来られた。申し訳なさそうに駅へはどう行けばいいのかと言うのである。 宝生能楽堂の玄関を出ると、すでに陽は西に移っていて老若の客が帰途を急いでいた。舞台にひたった昂りを鎮めてくれる夕風は心地よかった。私は上着のポケットから煙草を取り出しくゆらせていたのだが、ふと上品な小柄の老婦人が寄って来られた。申し訳なさそうに駅へはどう行けばいいのかと言うのである。
「どこまでお帰りですか?」と、問い返すと、さらに申し訳なさそうな顔をなさり、背伸びをするようにして「わたくし、耳が遠くなりまして」と、言うので今度は私がややかがんで耳側の、声を少し大きくしての会話になった。
「新宿方面から参りましたのですが…」
「それなら、この路地の坂を降りて大きな交差点をこう横断し、橋を渡ってガードレールまでいけば、そこがJRの水道橋ですよ」と指を差して説明すると、深々と頭を下げて礼を言われ、かよわい足取りで他の客にまみれて歩いて行かれた。
何とか無事、角を曲がる姿を認めたので玄関に戻ろうとしたが、あの雑踏で転んでは、と急に気がかりになり、私はとってかえして後を追うことにした。案の定、婦人は数軒先の雑踏の隅で立ち往生していられた。地下鉄の昇降口で降りようか、どうしようかと、迷っておられたのだった。やはり足元もおぼつかない。
私の顔を見ると、「すみません、せっかく教えて戴いたのに迷ってしまい」と、また子供のように謝られるので、私は婦人によりそって「ここではありません、ご一緒しましょう」と右腕を取り、駅まで歩くことにした。
「あなたさまも水道橋駅からお帰りですか?」
「いえ、また能楽堂に戻ります」
と返事すると、「それはいけません。一人で参りますので」と、恐縮してしまわれたが、余程、困っておられたのか、腕組みするとほっと安堵された様子であった。折れそうなほど腕が細かった。
信号を待っていると、婦人は切り出された。
「今日はほんとうに胸がいっぱいになりました」
「よかったですね。お能にはこうしてよくお出かけになるのですか?」
「いえ、この歳ですから、最近はとんと外へは参りません。実は、今日の舞台はどうしても観ておきたかったのです」
もう、失礼というものではないだろう、私が年齢を訊くと「九十四なんですよ」と、少しはにかんで応えられた。
「教師をやっておりました。この歳になって、自分の教え子があんなに立派になられ、こうして活躍しているのを見ますと、もう、この上なくうれしくて胸がいっぱいになりまして。はい、私はあの清水さんに高校時代、国語を教えていました」
一語一語確かめるように語る婦人は、うっすらうれし涙を目に浮かべておられた。そして「くれぐれも清水さんによろしくお伝え下さいませ」と、にわか響の会事務局の私に何度も託すのだった。
わずか百数十メートルの道行きで、私はなにか人の生のフィルムに映った一風景を見た思いがした。かつてどこにでもあった風景。人が他の仕合せを思い、育んだ。思われたもの、育まれたものは人世であるがゆえにほとんど師と同じ道を歩きはしない。遠く恩に報ゆる形があるとすれば、自分の道、自分だけの道を彊めることしか方法はない。私にそんな道があるだろうか。舞台で拍手をしない私は、ここで清水寛二さんに思いっきりの拍手を贈りたい気持ちにかられた。
水道橋駅の構内はごった返していた。路線図と値段の表示が見えないとわかり、私が発券機に並んでキップを求め、婦人の小さなショルダーバッグがきちんと閉まっているかどうかを確かめて、自動改札機まで人をよけながら進んで見送った。
改札でキップを通す直前、「歳をとると何もできません、駄目ですね」と、ポツリと洩らされた。そして「失礼いたしました。わたくしは秩父と申します。あなたさまは?」とおっしゃった。初めて名前だけの自己紹介をした。
長くて急なホームの階段を見上げて、秩父先生は再び足がすくんだようだったが、私に手すりがあるから大丈夫だと笑顔のサインを送り、深々とお辞儀をされた。昇降客に見え隠れしつつ踏み上がられた。ひとつの段を昇るのに三秒はかかった。中程のコンクリートの梁で姿が見えなくなるまで、何度も私を振り返られ、手すり片手にかわいいお辞儀をされた。
私の胸はとうに熱くなっていた。この日の十数分間、私は秩父先生の正真の生徒であった。 |
 |
| (いとう ゆうか・作家) |
 |
|
 |
|