|
|
 |
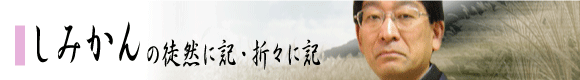 |
 |
 |
|
|
 |
 |
〔05/8/21〕長峰山の雲 |
【008】 |
 |
|
 |
昨日は信州明科(あかしな)町での薪能。松本から篠ノ井線で二駅「明科」下車。(私たちは松本駅に町の職員の方が迎えに来てくださって車で。直接京都や東京から車で来る役者も多い。)正式名称は「水郷明科 薪能」。龍門渕公園にて。
京都の青木道喜さんの父上故青木祥二郎氏の出身地。今年で15回目。私はお邪魔して4回目くらいかな。今年は「正尊」(シテ道喜氏)のツレ「姉和(あねわ)」の役、普段出来ない役をやらせていただいて真にありがたい。(正尊は鎌倉の頼朝から京都の義経に差し向けられた刺客。弁慶と同じく僧形。姉和と書くと女っぽいが、正尊の郎党頭「陸奥の国の住人 姉和の平次光景」。大将を討せじと弁慶と奮戦し討たれる。正尊も結局縄かけられる。)
去年は青木さんの新作能「犀龍小太郎」(龍の子太郎の話)で、私は小太郎を育てた「おばば」の役だった。(長峰山のおじが茂山七五三さん。)一昨年は「安宅」の山伏頭。その何回か前に一度新作能「永訣の朝」の地謡で。
大体が京都の人たち、今年東京からはワキの宝生欣哉氏一行と狂言の野村萬先生一行と私。
20名以上のシテ方でただ一名の東京者で大いに緊張するところだが、京都の人たちは礼儀正しいが、大先輩から若い人まで結構皆和気藹々とやっていて、楽しい楽屋で居心地はまあまあ。
青木さんからは清水さんがいてくれるとみんなの刺激になると言っていただいて恐縮至極。
姉和の役は銕仙会などでは普段もっと体力的な人がやっていて機会がなく、初役。実は冷や汗タラリ。
相手の弁慶役の欣哉君が実に気が入っていて、斬り組も気持ちよく、仏倒れもまあまあか(その瞬間は本当に怖いが、やるしかないと思って・・・)、きっちり頭から落ちて無事死んで帰った(京都では頭を打たないようにやるらしいが私は先代銕之丞に頭から落ちて、ケガないようにと習っている。しかしあとで後遺症が来るかも)。能では死んだはずの人が自分で歩いて帰るのだ(転がってたら大変だけど)。
番組は五時半から仕舞が数番。これがえらい強風の中で始まった。扇を開いて高く上げるところで飛ばされそうになっている。これが薪能の困るところ第一点。萬先生「こりゃ作り物のあるだったら出来ないね。」次に狂言の紹介のアナウンスの間に雨がポツリポツリ。そして結構強く。これが薪能の弱点二号。萬先生にはしばらく待っていただくことに。狂言は「茶壷」。しかしさすがに地元に通じた青木さん、土地の古老に聞けば「あの雲がもっとこっちから出てくれば大変だがあそこから流れてるから15分ぐらいで止むだろう。」との事。実にぴったりその通り。舞台に敷いたブルーシートをはずして、からぶきして、再開。お客様もじっと待っててくれました。
薪能の主催者、そして承りの人はなかなか大変。自然が相手じゃね…。見る側から見ればその不確定要素がなかなかいいということにも。明科薪能、町の人総出で舞台設営から何から何まですべて一生懸命やってくださっているようで、とても気持ちよい催し。(つくばの明野薪能も。そうだ両方明るい。)あとは(舞囃子「西行桜」片山九郎右衛門師と「正尊」)最後まで無事だった。残念ながら満月は長峰山と雲に隠れて見えなかったけれども。
*「船弁慶」に「あの武庫山颪ゆずりはガ岳より吹き降ろす嵐に」という一節有り。
萬先生には6月の銕仙会で初番のワキが開演時間に間に合わず「先に狂言をやりましょうか」と言っていただいたこと有り。今回は再開までじっと端座して待っていらした。その装束姿の美しいこと。お客様のほとんどが初めて萬先生の狂言を見る人だったでしょうが、きっと皆さん満足して帰られたことだと思います。(初めて仏倒れを見た人もオオーと思って帰っていただいたかしらン)
無事終演後、結構皆さん車で京都、東京まで帰る(どうぞお気をつけて)。泊まる人は町営の「長峰荘」。青木さんの教えている立命館の学生たちもいて(関東の連盟の会で見た早稲田の人たちはうまかったと言ってくれる。ありがとう。また交流してください)、大広間は延々、午前3時。青木さん元気。
最年長武田欣司さんにいろいろ伺う(いつも後見で大活躍。若松さんくらいのお年か)。それからいっしょに風呂に入って(改装されてきれいになった。露天風呂もなかなか、のラジウムイオン鉱泉。月は雲間に見え隠れ。)寝る。
6時半には京都への第一陣帰る。朝風呂を浴びて(北アルプスがずっと見える、ただし山頂付近は雲。ちょうど向かいは常念岳)、私も8時45分明科発の電車(松本より特急あずさになる)で帰る。明科駅は、ミンミン蝉。
一旦うちに帰って夕方に梅若の山崎英太郎氏のお通夜。(ご子息の山崎正道君とは今度の「原爆忌」でも一緒。)しばらく前にお倒れになって、残念ながらこのところその温顔に拝することなく逝ってしまわれた。ご冥福をお祈り申し上げます。
明日よりは「原爆忌」に集中と言うか多分時間がなくてしばらくお休みだろうと思います。28日に鹿児島から帰って書ければその時。では。
* 「槿花一日の栄」は能「敦盛」に有り。「槿」は「あさがお」?
* 「三五夜中の新月の色」は能「三井寺」に有り。満月に狂女。
* 空手をやっている麻耶が所属している会の全国大会にて型で三位。「石の上にも三年」。
小さくても人一倍稽古をしたから。さあ後は卒論だよ。
* ソフトボールの沙羅は国体の関東予選で負けて国体本戦出場無し。まことにざんねん。
但し日韓交流の選手に入って9.1よりソウルへ。
* 9.2「響の会」研究公演では私も舞囃子「天鼓」を舞います。勅命により湖に沈められた少年天鼓の霊が、秋の水上で鼓を打って舞い遊びます。舞囃子は紋付袴姿で一曲の舞どころを舞うものです。どうぞ皆様いらしてください。 |
 |
 |
〔05/8/19〕三五夜中の新月の色 |
【007】 |
 |
|
 |
今朝は桔梗の花の開くところを見た。(前から一株あったのだけれど、紫式部が茂って見えなくなってしまったので、かみさんが280円で買ってきて日の当てるところに植えた丈の低いもの。)蕾の先が少し切れていたのでしばらく見ていたら、パキッと音がして、いえいえそんな音はしません、知らない間に「ふと」咲いているんです。鮮やかな紫。昔はこれを朝顔と言ったという。なるほど、朝咲く。
今言う朝顔、夏の盛りより実は今頃からが花の盛りかな。タッちゃん(小学一年生。なかなかきかない顔。中学一年生のお兄ちゃんにサッカーを仕込まれて一生懸命練習している。)ちの庭に青の朝顔がきれいにつながって咲いているのを見つける(ヘクソカズラも)。そういえばいつも月末の鹿児島の入来の薪能の時、移動のバスから少し薄い青の朝顔がたくさん見える。
「槿」は「むくげ」で出てくるが、むくげというと「木槿」という感じ。このところずっと盛りでよく咲いている。それぞれの木で色が少しずつ違う。同じ白でも花の奥のほうに少しえんじがあったり。暑さの中に涼やかで、清楚で、しかもたくさん咲いて元気で、とてもいい花。朝鮮の花と聞く。
今日は午後より青山でお弟子さんの稽古。少し私の乗らない様子から「今日はみんな一科目」と言ってくれる。「仕舞」と「謡」のどちらかということ。助かった、と言うよりゆっくり出来る。
9時までやって少し自分で動いて帰ってくれば、満月に近い大きな月。三かける五で十五夜。満月が「新月」だったんだね。新月はあ、「朔月」かな。
明日は信州「明科」の薪能。月光の北アルプスが背景に。
シテ・青木道喜氏の「正尊」。私はツレの「姉和」の役で、久しぶりの「仏倒れ」(斬られて死ぬときのやり方のひとつで真後ろに倒れる。私は宝生欣哉氏の弁慶に斬られる)。無事に帰ってきましょう。 |
 |
 |
〔05/8/18〕落蝉 |
【006】 |
 |
|
 |
昨日はもっと文章を書くつもりでいたのに書き出しで終わりになってしまった。題名の由来はいずれ。
今日は順扇会(山本順之氏の会)の夏のおさらい会(浴衣会)。於青山。(「青山」というのは銕仙会舞台あるいは観世銕之丞家の略称。戦前は下谷西町にあったのでいまだに「西町」という人もいる。)
11時から5時過ぎ。素謡を何番かと仕舞の地を何番か謡う。少しでも謡ってないと声も言葉もなかなかスムーズに出てこない。
しかも一昨日大腸の内視鏡検査をやり(初体験)、ポリープをひとつ取った。そのせいかなんだか集中しない、少しふらふらするような気がする。宴会に誘われたが、珍しくお断りして帰る。お酒は2,3日控えてと言われたので、うーん・・・。
駅を降りて家への途中に桜並木があるが、今日はもう蝉と秋の虫の二部合唱。バサと目の前を蝉が落ちる。
もう満月に近い大きな月。長崎で浦上のたいまつ行列の上に出ていたのはきれいなほっそりとした三日月だった。
もう明日からは休みもなく秋の臨戦態勢に突入かな。
また今日もこの辺で終わろう。おやすみなさい。 |
 |
 |
〔05/8/17〕槿花一日栄 |
【005】 |
 |
|
 |
今日は一日家にいる。冷房に当たらないからいい。日中暑いは暑いがさすがに立秋をすぎ、処暑にならんとすれば(殊に昨日のまとまった雨が良かった。)朝晩涼しい。もう秋の虫も鳴きだした。
朝まずソフトの練習に行く沙羅を送り出し(6:30)、昨日夜の花火のあとをかたづける。今日は土も湿ってお日様は元気そうだが涼しい。
ああ白百合が咲いた。道に出ているので切って仏様に。 |
 |
 |
〔05/8/11〕クマゼミの なくや大楠 白百日紅 |
【004】 |
 |
|
 |
今朝は久しぶりにざっと雨。あわてて窓を閉める。昨日は折りよく座間市民ホールで宮沢りえの「父と暮らせば」をやっていたのでかみさんと見た(市と原水禁の主催、無料、少しカンパ)。そして国立にて「原爆忌」の稽古。それから笛の松田氏と「長崎の聖母」他の打合せ。とてもよい提案を頂いた。
8・9・10日は長崎に行っていました。全部書くのは大変なので要所を書きます。
8日
昼食 「吉宗」(よっそう)本店にて名物の角煮の入った定食。米久を思わせる二階の入れ込み座敷。少し昼に遅かったのでほとんど貸切。
4:00 長崎新聞にて取材。終えてから原爆爆心地を経由して浦上教会へ。爆心地では長崎の宗教者会議の方々による慰霊祭の準備中。神道、仏教、キリスト教、イスラム・・・色々な宗教合同での慰霊祭。以前お世話になった諏訪神社の方にもお会いした。残念ながらゆっくりとどまることできず浦上へ。浦上天主堂はNHKの平和コンサートの準備中。今日が公開リハーサルで明日が本番。今日明日ともに見学できることになっていて、客入れ前から見せていただく。オーケストラ用に舞台の張り出し、客席を8,9列取っている。これは私たちには出来ないが、いくつかの点でヒントあり。終わって打合せ、そして一献。
9日
6:00 浦上教会ミサ。平野主任神父が司祭。
8:30 純心学園慰霊祭(ミサおよび墓前祭、中高校にて)。同じく平野神父。神父の言葉、墓前祭での代表の方々の言葉胸にしみる。グラウンドに大きな楠が何本か。復活の大楠。
10:00 浦上にて舞台設営について打合せ。以前の案に対し、新たな提案を二つほどする。OK。
10:30 被爆のマリア像の小聖堂の献堂式。
引き続き浦上教会原爆慰霊のミサ。大司教が司祭。11時2分黙祷。信徒の方々で教会堂はいっぱい。信女の方々はべール(「長崎の聖母」でも使う予定)。この方々に見ていただくと思うと身が引き締まる。(同時刻に行われていた平和公園の式典へは行かず。あとでテレビで様子は見る。)
純心の大学、短大を見学。郊外の「三山」に有り。中心部からは山向こうなのでここにいた生徒たちは助かった。永井隆博士の子供たち誠一さんと茅乃さんもこの三山のおばあちゃんちにいて助かった。永井博士の第11救護隊の記録にこのあたりが詳しく出ているので一度訪ねてみたかった。きれいな山川に沿ってぽつぽつと集落が続く。大学は一番上、大村湾まで見える環境のいいところ。雪が降ったら大変そう。
14:00頃 市内に戻って昼食、そば。さっき浦上のミサで見かけた外国人の老夫婦が入ってきた。注文に困っていたが、奥さんがてんぷらそば、旦那さんがライスとミソスープにビール。
19:00 浦上天主堂NHK主催の平和コンサート。実況中継。吉永小百合さんほか。
19:30 堂前よりたいまつ行列が平和公園へ向って出発。アベマリアの歌声、ゆらめく松明が向こうの丘まで続き、美しい。(昼間の外人夫妻も松明を手に。)行列についていき、平和公園でのミサ、別のコンサートなどの様子を見てまた天主堂へ戻る。終わって平野神父や純心の片岡学長にお目にかかる。
21:30 おすし屋さんにいたら、さっきのコンサートで「鳥の歌」を弾いたチェリストが現れすし折をお土産に帰る。
10日
9:30 浦上天主堂。ばらしの様子を見ながら舞台を確かめる。
10:00 永井記念館。館長徳三郎氏にお目にかかる。前館長誠一(まこと)氏に原爆慰霊の能を作りたいと申し上げたこと有り。報告やらお願いやら。また誠一氏急死のあと館長になられたことなどいろいろお聞きする。
11:00 NHK長崎支局訪問。副局長にお目にかかる。
12:00 長崎大学医学部(当時長崎医大)の原爆資料室。写真展、ビデオ見る。傾いたままの旧正門門柱。大きな白い百日紅。
18:30 少し遅刻して東京国立能楽堂での「原爆忌」の稽古に出席。多田先生ご夫妻もいらしている。今日は楽屋で全体を謡ってみる。
ちょっと時間がなくなってきたのでバランスがどうかわからないけれどざっとのみ。「長崎の聖母」への収穫等についてはいずれまた。今日も夜は原爆忌の稽古。 |
 |
 |
〔05/8/6〕花火の爆音 |
【003】 |
 |
|
 |
私の住んでいるのは神奈川県座間市。全国的にわかる人がわかるのは「日産」と「米キャン」。日産の座間工場が撤退して久しいが、何も全部がいっぺんになくなったわけではなく、どれがどの工場だかわからないが、今も工場群はある。日産座間から撤退のニュースが流れた頃、税収が減って座間市の財政がやっていけなくなるだろうとよく言われたものだが、一体どうなっているのだろう。立派な新市庁舎やホールを作っていたのか作ったばかりだったのか、ともかくそんなもの作ってやっていけるのかという話題が出たものだった。まだそのままだから、やっていけてるのだろうけれど・・・(11月に薪能があるので座間市のことはいつかまた触れるでしょう。)
もうひとつはアメリカ軍の座間基地(キャンプ座間)。この辺では「米キャン」。最近の話題では、ジェンキンスさんがいたこと(駅前のスーパーで曽我さん親子が買い物しているのに遭遇したことがある)や、大きな司令部をここに移そうとしていることなどがある。戦前はここに陸軍大学校があり、戦後接収されてアメリカ軍と自衛隊の基地となった。(たまたま引っ越してみたらここだったので、引っ越してくるまでは、そしてしばらくもよく知らなかった。)駅の名の「相武台前」もそこからの名前で、最近の「何とか台」とは違ったのだ。駅前の相模大野方面へ続く道も「行幸道路」、天皇の通った道だったのだ。(この米キャンへ宝生閑氏は戦後すぐジャズバンドのアルバイトによく来て、結構おこずかいになったと聞いている。)
今日は米キャンの花火だった。いつもは基地内(すごく広くて芝生できれいでゴルフ場もあって・・・)に一般人は入れないのだが時々開放日があって、今日はそのひとつ。毎年花火が上がる。独立記念日にも前は花火をやっていたと思うけれど例の9.11からやめたのかもしれない。さて、今日は何の日なんだろう(言うまでもない、広島の原爆記念日)。
我家は高台にあってすぐそばの土手になっている道から、谷をはさんで向こうの丘の上に花火が良く見える。近所の人が三々五々出てきて、タッちゃん一家も、福ちゃん(これは黒ワンの名)一家も、みんな出てきて見ている。8時半かららしくちょうど家は一人で音がしてから見に行った。
このあいだは神宮の花火(8.1)を、これは多田富雄先生の家(昨年完成)を設計された岩崎さんの事務所(千駄ヶ谷の駅前近くのビルの7階)で見せていただいた。多田先生ご夫妻もいらしていたが(奥様のさりげなくグラスや料理などをかたづけるやり方に感心)、その時の多田先生の一句「面白うてやがて悲しき花火かな」。(あ、これはどこかに発表なさるまで内緒かな?) 1万発の花火、なかなかすごい。昔より質量共に花火の技術がずっと進んでいるんでしょうね。そしてコンピュータ制御かな。しかし多田先生がどうですかと聞かれて「昔」と仰ったのは昔の素朴な花火に風情があったということかと思う。(多田先生は多田富雄、新作能「一石仙人」や今度長崎で上演する「長崎の聖母」の作者、免疫学者。4年前に脳梗塞に倒れ現在は車椅子を使用、会話もキーボードを片手で打たれての会話機を通じて。ただし目はしっかりとして物事を見据えている。また打ち解けて大きく笑われるときは失礼ながらとてもかわいい。)
もうそろそろ終わりかと思って後ろを振り向くと、一番下の娘とかみさん。おじさんと呼んだんだけど、などという。俺はおじさんじゃないから聞こえなかった。今日も彼女は練習。そして厚木で優勝パレードもあったのだ。そう、インターハイで見事優勝(春の選抜と全国二連覇)。私も応援できました。(おかげで両腕は日焼けで真っ赤。いてて) 応援していただいた方々ありがとうございました。
厚木商業のえらいのは(もちろん監督の利根川先生によるもの)、試合が終わって、表彰式がありバスやお父さんたちのワゴン車などに分乗して学校まで帰ったら(首都高が事故渋滞でついたらもう9時過ぎだった)、その使った道具やいろいろなものを片付けるのに三年生から全員で、(あの炎天下で準決勝と決勝と二試合を全力でやったのに)実にきびきびと速やかなる事。そして翌日はいつもと同じ6時半に出かけて、中学校二校が来ての(中学の関東大会へ向けての)壮行試合。彼女たちの合言葉「GET
WIN WITH SMILE」の通り、グラウンドで実ににこやかなこと。よっぽどいつも厳しい練習をしてるから出来るんだなとも思う。ピッチャーがいいからだが、炎天下毎日何時間もノックを受けて練習してきたライトの沙羅の所へはほとんど打球は来なかった。だけどその全員の努力が優勝を導いた。準決勝も決勝も1-0、相手チームもがんばってきたんだ。だけど全く負ける気を起こさせない何かが彼女たちにはあった。ありがとう。
しかしお父さんお母さんたちも大変。私は最後の応援にしか行ってないから申し訳ないが、仕事がずいぶんあるんだ。そういう意味でも伝統が必要だ。試合の応援だけでも、あれだけきちんと水分の補給まで考えて仕事分担している。(あんなに水分を取ったのは近年なかったぐらいです、そうしなければ倒れていたかも。)ありがとうございました。
そして花火。米キャンの花火も(バックが丹沢で暗いから条件では神宮より有利)なかなか良かったきれいだった。最後はだんだん大きくなって一番大きな柳で終わった。沙羅「すごーい。音もすごいね。でもこれ戦争体験のある人だったらどうだろうね。」「そうだね、つらい人もいるだろうね。今が平和だからできるんだな。」
私もこの前の神宮のときからそれを考えていました。(殊に今「長崎の聖母」をテーマとして追い込んでいるからかもしれません) 花火は今みんなきれいだと思ってみていられますが、現象として言えば爆発ですから、空襲警報、照明弾、焼夷弾、艦砲射撃、機銃掃射、・・・原爆。B29もすごかったでしょうね。昔沖縄の嘉手納で見たB52の離陸の様子を思い出します。あれが空襲にきたら・・・。今厚木基地(大和市にあります)からアメリカ軍のジェット戦闘機が編隊で低空飛行するところ、すごい音です。
ああもうちょっと体力がありません、おやすみしましょう。
そうそう子供たちが小さい頃虫干しの帰りに神宮の花火に行ったんです。球場の近くで「どーん」となったら「こわいー」で帰りました。
八月九日は長崎へ行ってまいります。純心学園と浦上天主堂のミサと平和記念式典に出席してきます。「長崎の聖母」の本出来上がって先日集まって稽古いたしましたが、もうひとつ詰めたいと思っています。 |
 |
 |
〔05/8/4〕紅白の水引 |
【002】 |
 |
|
 |
今日も朝から暑い。庭の鉢たちに水をやる。トカゲがチョロチョロ、あらシジミチョウが今日は多いね。実生を鉢にしているケヤキの葉が少し黄色くなった。少しもう鉢が小さいか。
生垣の左右に赤と白の水引が咲いている。うまい具合に出たものだ。赤のほうが先に咲き始めて、あとから白が咲いたが、この花は近くによってじっと見なければわからないぐらいそれぞれの花は小さく(花びらなのか、それは2mmか3mmか)、しかし愛らしく美しい(わずかだが赤のほうが大きい)。しかも紅白とはめでたいものだ。
銕仙会の事務所で主にチケットを担当していた川村さんが先月いっぱいで退社された。長い間お世話になりました。銕仙会のチケットだけでなく、例えばこの響の会のチケットなども今まではほとんど川村さんにお世話になっていた。お客様でも常連の方々は川村さんと親しかったはずである。我家の引越しも手伝っていただいたし、子供たちのこともいつも気にかけていてくれました。ありがとうございました。新生活、お体をいとって楽しくお過ごしください。
昨日は国立能楽堂で『船橋』シテ観世銕之丞。世阿弥が田楽の能から書き直したという古風な能。やるのは少し難しいと思うが、万葉の東国が偲ばれるよい能。私は山本順之師と後見。シテの前後装束をつけたが(前は薄墨大口に掛素襖、後は紺大口、袷法被に大水衣を重ねる。面は白平太)、まだまだバッチリとはいかない。ようやくあせらなくはなって面白く思うのでもう少し、もう少し。
これでしばらく私は公式の催しはなく、紋付もお休み。つぎは20日の信州明科の薪能。京都の青木道義さん承りの催し、今年は『正尊』(私は後のツレ「姉和」の役を頂戴している)。その間いくつかの稽古や長崎訪問もあるが、この暑さの中で体と心をゆるめよう。(幸い我が家は冷房がない(テレビもない)ので助かる。)そして秋に備えよう。
昨日国立の能は午後だったので、夕方より東京三菱銀行の謡曲部のお稽古(丸の内の本店にて)。その後暑気払いに会員の人とビールをと思っていたのだが、響の会の臨時運営委員会をやることになってそれに出席。議題は発行が遅れている通信のことや秋の催しの運営について。結局最終電車で帰る。(新宿駅12時20分発相模大野行き急行、相模大野から各駅停車相武台前行きの最終となり、この相武台前が私の最寄り駅。)うちに着いたら1時半、長女の麻耶がポテトサラダをたくさん作っていたのでそれを頂いて、「おやすみ」。
今朝は麻耶が空手の稽古に早く出かけた。(國學院大學空手部、4年生、2段らしい)毎日練習ばっかりで早く就職を決めようよ。
その上の蓮太郎は「石っ子蓮さん」。大学院で鉱物をやっていて毎日実験で遅い。昨日は私よりは少し早かったらしいが、まだ「うーん」といって寝ている。この間新発見をしたらしいので、そのことはやがて紹介しましょう。
次女の伽耶は今年の春から大阪の大学へ行きました。試験等はすんだらしいがマンドリンのクラブに入っているらしくまだ帰ってこない。明日は一番下の沙羅がソフトボールをやっていて、インターハイ(全国高校総体)に神奈川県代表で出ていて(県立厚木商業高校)、その決勝戦が成田であるのでそれに帰ってくるかもしれない。
かみさんはその応援に初日から行っている。甲子園を思っていただければよいのだが、周りでサポートすることも多く、父母会全員で行っている。決勝戦まで残るかどうかわからないだろうと思われるだろうが、新聞ではダントツと書かれていたし、(いやそんなことはないよと自分たちは謙虚に言っている)、春は全国選抜で優勝したが、学校に帰ってすぐグランドで練習するぐらいのチームが、なかなか負けるものではないようだ。しかしやっぱり勝つことには難しいこともあるだろうから、ガンバレ。
幸い明日は予定がないので私も応援に行く予定。いつも父母会のお父さんたちは練習試合の審判をやったり、グランド整備を手伝ったり、車を出して遠征などの送迎をしたりがんばってくれています。私は時間も車もなく、なかなかお手伝いできず、大きな大会の応援にもなかなかいけず、申し訳ない。(ことに4番打者の田中梢子ちゃんのお父さんいつも沙羅を乗せてもらってありがとうございます。朝4時とか5時とかに迎えに来てくれることがあるのです。そして同じ三年生のシゲ、ウメ、ウッチー、タッキーのお父さん、二年生の土屋さんほか皆さんのおかげです、ありがとうございます。)
優勝の興奮をもらいに明日は成田へ行ってきます。今日は午後より銕仙会にてお弟子さんたちの稽古です。では行ってきます。
■ 補記:お問い合わせに答えて
・銕仙会の歌仙会および虫干しは残念ながら公開しておりません。あしからず。
・「米久」よねきゅう。「米久の晩餐」は高村光太郎の詩にあります。読んでそして出かけてみてください。
・米久の女将さんは丸山圭子さん。同じく丸山冨美子さんは、根岸の洋食屋「香味屋」の女将さん。先代銕之丞の古いお弟子さんで、とてもきっぷがよく、「あら先生そんなこと言ったってねえ。」と先生もたじたじの時もありました。実に熱心でよく稽古もされましたし、舞台もよくご覧になっていました。このところ少し体調を崩されているのは残念です。どうぞまた「清水君がんばってる?」とハッパをかけてください。 |
 |
 |
〔05/7/27〕米久の晩餐 |
【001】 |
 |
|
 |
台風が去って今日はかんかん照り、蝉君たちが元気を出してくるだろう。
銕仙会の前期のまとめは7月末の歌仙会と一週間の虫干し。今年は21日が歌仙会。舞囃子(能の舞所を囃子を入れて舞うもの)を36番、交代して切れ目なく舞う。朝8時に始めて今年は午後6時半過ぎ終了。私は「遊行柳」と「九世戸」を舞い、地謡を8番ほど。遊行柳は老柳の精がシテ、サシ・クセから序の舞、キリまでとかなりの分量があり、40分ほどかかったか。これに対して九世戸は天橋立の竜神がシテで、働きとキリだけでテンポも良く10分はかかってないだろう。昔の立替前の舞台では冷房もなくほんとに汗みどろだった。今は冷房もあり、楽屋も広くなってずいぶん楽になったが、それでもこの一日を乗り切るのはなかなかだ。寿夫先生は基礎に立ち戻るときだと仰っていた。終わったあと参加者全員でビールでのどを潤し語らいのときを持つ。和やかにと言いたいところだが時には師匠や先輩からの批判で非常に厳しい時間ともなる。
私の遊行を見て長山禮三郎さんが奥善助さんに似たところがあったと言ってくれた。そうしようとは全く思っていなかったのだが、実は舞っている途中で善助さんの姿を二度ほど思った。クセの途中の蹴鞠のところで善助さんの姿がふと浮かんだ。そして序の舞の途中で(自分が少し大またになっている感じがして)ああ善助さんは以外に大またの時があったなと思った。不思議な体験だった。今年も青山を出たのは12時をすぎていた。
そして翌日からは装束と面の虫干し。舞台や楽屋に毎日違うものを干してはお蔵に仕舞い直していく。これも毎日やるとなかなかの行。綱を舞台の柱と柱の間に張り巡らし、装束や面のおかげで能が舞えるのだからこれらに感謝しつつたとうから出し、全部の装束を広げて(中には一年でこのときしか出ないものもある)ハンガーで干す。傷んでいるものは修理をする。たとうも修理をして使っているからつぎだらけ。そしてたたんでしまう。毎日違うものを干すのだが5・6日かかる。楽屋や他の場所で小道具類や紐の類、鬘帯・腰帯などを干す。
最終日は大体面の日となっている。200面以上ずらっと並ぶ。一年にこのときしか見られない面は多い。なるべく一面一面と対峙しておくつもりだが、あんまりありすぎて一つ一つの印象が薄れるくらいだ。
この毎日に前期でやったことを思い、また秋にやるものに何を使おうかなどと考える。・・・つもりだが実際は体力勝負できびしくなかなかきちんと物事を考えられるものではない。(今年はやっとのことで11月の『長崎の聖母』の節付に終始。) などと言いつつこれが、前期の締めくくり。
それが昨日だった。そして打ち上げは浅草の牛鍋の米久の予定だったのだ。しかし台風!。電車が止まるかもということで、(そういえば虫干し途中の地震の時がそうだった)あえなく中止となってしまったのだ。ああ「米久の晩餐」!
この米久の女将さん(丸山さん)にはよく能を見ていただいている。東京の銕仙会などはもちろんだが、金沢の一石仙人も見ていただいた。今秋の長崎にも来て頂けるかもしれない。ありがとうございます。
ああ今年前期も結構良くがんばった。さあ浅草へ行くのだべし。 |
 |
|
 |
|