|
|
 |
 |
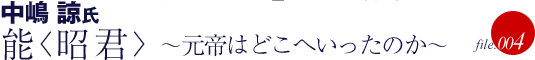 |
 |
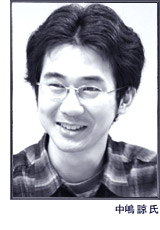 王昭君の逸話は、いわゆる「王昭君伝説」として、古来好んで語られてきました。そもそも王昭君については、古くは中国の歴史書『後漢書』(巻七十九)にその記述があります。その記述は、きわめて簡潔なもので、①王昭君が後宮に入りながら元帝の寵愛を受けられなかったこと、②王昭君が漢と胡国との友好のため呼韓邪単于のもとへ嫁いだこと、③王昭君が呼韓邪単于との間に二子をもうけたこと、などが淡々と記されています。のちの多くの王昭君の逸話は、この『後漢書』の記述をもとに着色を重ね、語り継がれていったものだと思われます。 王昭君の逸話は、いわゆる「王昭君伝説」として、古来好んで語られてきました。そもそも王昭君については、古くは中国の歴史書『後漢書』(巻七十九)にその記述があります。その記述は、きわめて簡潔なもので、①王昭君が後宮に入りながら元帝の寵愛を受けられなかったこと、②王昭君が漢と胡国との友好のため呼韓邪単于のもとへ嫁いだこと、③王昭君が呼韓邪単于との間に二子をもうけたこと、などが淡々と記されています。のちの多くの王昭君の逸話は、この『後漢書』の記述をもとに着色を重ね、語り継がれていったものだと思われます。
たとえば『今昔物語集』(巻十)では、王昭君が胡国へ送られた経緯、つまりは王昭君が絵師に賄賂を送らなかったために肖像画を醜く描かれてしまったこと、などが詳細に述べられています。能「昭君」もこういった逸話の一つであると考えられますが、ただ能「昭君」は他の多くの逸話と、いささか趣を異にしています。能「昭君」では、前場で娘
王昭君を失った老父母の悲しみが、後場で老父母と王昭君及び呼韓邪単于との対面が描かれますが、まず「老父母」というのは、他の王昭君の逸話には全く見られない登場人物であります。また王昭君が入った後宮の主
元帝の存在が、一切語られることがありません。たとえその寵愛が受けられなかったとしても、王昭君について語られる上で、王昭君の元帝に対する思いが一切語られないのは、いささか不自然なのではないかと思われます。
中国の13~14世紀 元の時代に、「元曲」という演劇が流行しました。その題材はさまざまですが、王昭君を題材にした「破幽夢孤雁漢宮秋(幽夢を破る孤雁漢宮の秋)」という曲もあります。そこでは、王昭君と元帝が相思相愛であって、胡国へ連れ去られるにあたって悲しみのあまり自殺をしてしまう王昭君と、それを嘆き悲しむ元帝の姿が描かれます。能「昭君」も、もしも元帝を登場させたならば、元曲「破幽夢孤雁漢宮秋」のような王昭君像を描くことができたはずです。それにもかかわらず他の王昭君の逸話に全く見られない老夫婦を登場させ、その一方で元帝を登場させなかったのは何故なのでしょうか。
ところで能「昭君」においては、「柳の木」というものが、非常に効果的に謡われています。老夫婦は、「柳の木の下」に亡き王昭君を嘆き悲しむのです。ただ先にも挙げました『今昔物語集』を見ますと、「柳の木の下」に悲しむのは元帝なのであります。能「昭君」は、特にクセの部分において『今昔物語集』の記述を大いに参照しているように窺えますので、おそらく能「昭君」の作者は『今昔物語集』を読んでいたといって間違いないでしょう。しかしそれにもかかわらず、能「昭君」の作者が「柳の木の下」に悲しむものを、元帝ではなく老夫婦にしたのには、何か特別な意図があったのではないかと思われます。おそらく能「昭君」の作者は、元帝の悲しみを語るだけにはとどまらず、王昭君の父母の悲しみをも語るために、あえて前シテ・ツレを老夫婦にしたのではないでしょうか。言い換えますならば、能「昭君」の前シテ・ツレの悲しみには、元帝の悲しみも含まれているのだと考えられます。
以上は私の勝手な思いつきではありますが、響の会にて能「昭君」がどのように描かれるのか、非常に楽しみにしています。 |
 |
| (なかじま りょう・早稲田大学観世会OB) |
 |
|
 |
|