|
響の会通信第九号拝読。冒頭二氏の文章を始め、荻原氏との対談、茂山氏の文章など、役者側の能に対する真摯な思いが伝わって来た。これだけの役者側の危機感に対して、観客である私達がどう応えて行くのか、これが今の能に最も求められている事ではなかろうか。
能に対する需要が尽きかけている。この事を我々観客は演者よりも更に真面目に、大きな視点で受けとめなければならないのではないか。日本人が能を見なくなった、この事がどれ程重大な事なのかを、自分達の問題として考えて行かなければ、やがてとんでもない事になるだろう。これは決して役者の努力不足の為ではない。もっと大きな流れの中で、われわれ日本人は、一大転機にさしかかっているのである。この事に対して、心ある日本人は、どんなに熱くなってもなりすぎではない。今熱くならずして、いつ熱くなるのか。
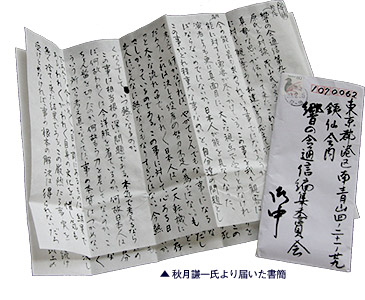 この事は相当根の深い問題である。本気で考えるならば、何故われわれは今洋服を着ているのか。何故日本人はちょん髷を切ったのか、何故もう刀を差していないのか、こういう所から考え直さなくては、事の本質はつかめないであろう。今われわれの目の前にあるものは、結果である。われわれが、われわれ自身の文化を、惜し気も無く捨てて来た結果である。この厳然たる事実を受けとめなければ、事の根本の解決は得られないだろう。今やわれわれの日常の生活の中の意識、又生活様式の延長線上に、能は無いのである。能と言われてピンと来る人が、一体どれだけ居るだろうか。需要が無くなって行くのも仕方の無い事ではないか。 この事は相当根の深い問題である。本気で考えるならば、何故われわれは今洋服を着ているのか。何故日本人はちょん髷を切ったのか、何故もう刀を差していないのか、こういう所から考え直さなくては、事の本質はつかめないであろう。今われわれの目の前にあるものは、結果である。われわれが、われわれ自身の文化を、惜し気も無く捨てて来た結果である。この厳然たる事実を受けとめなければ、事の根本の解決は得られないだろう。今やわれわれの日常の生活の中の意識、又生活様式の延長線上に、能は無いのである。能と言われてピンと来る人が、一体どれだけ居るだろうか。需要が無くなって行くのも仕方の無い事ではないか。
それなのに、では、何故、われわれは能を観るのか。日常とのあまりの隔たりに、何となく違和感を覚えながらも、能を観ると何だかほっとするのは何故だろうか。
それは思うに、われわれ日本人は、能の中に、民族の祈りを見る のではないか。色々な事がこの国であったが、いつかこの場所にも平和が来ますように、数え切れない人達が死んで行ったが、誰一人残らず救われますように。この様な祈りと、又その事への確信が、能という芸能を生みだしたのではなかったか。しかもそれが、われわれがまだ心のどこかで捨て切れない、日本人の文化(もの)として、今も目の前に存在することに、言い様の無い安心を覚えるのではないか。いくら外国のものをとり入れても、様々な機械を使っても、達成出来なかった事が、生身の人間によって、自分達の文化として、今、目の前で達成されている。大声で自分達の言葉で、天下泰平とうたっている。こんな幸せな事があるだろうか。これがなくなったら一体われわれはどうすればよいのか。能を葬り去ってはならない。決して葬り去ってはならないのである。
役者の方々が、ギリギリの状況にあって、能を舞い続けて居る間に、われわれは、それと同じだけの、いやそれ以上の覚悟をもって、自分を見つめなおし、人間について考え、日本とは、日本人とは何かを問いなおし、文化の復興、そして創出を通して、能の存続発展の為の環境を作って行かねばならない。この民族存亡の危機にあって、われわれはあらゆる妥協を廃して、その原因と、これから目指すべきものを追求して行かねばならない。その為に能は、多くのものをわれわれに教えてくれるであろう。今程能の力の求められている時は無い。日本の復興と芸能とは不可分である。
私は一日本人として、この事に全力を注ぐ事が出来る様にと、切に祈る者である。
そしてその為にも是非、能にはいつまでも、「面白い」ものであってほしい。朝太陽が顔を出した瞬間、ふわっとすべてが明るく照らされる様な、そういう光を放ち続けていてほしいと思うのである。
|