|
|
 |
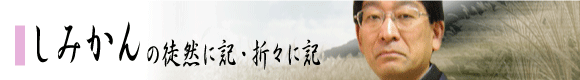 |
 |
 |
|
|
 |
 |
〔05/10/28〕原始野の秋の草と三鈷の松 |
【017】 |
 |
|
 |
今日は10時から「長崎の聖母」の稽古@青山。今日は立っての初め。囃子方3人九州より来てくれる。前回まあまあいけそうだったのに、今回は少しごちゃごちゃしたところあり。次回はまとまりたい。私のシテの演技はどうか。能舞台でない分余計に、全体の演出としての責任もあり。
またもともと8月9日の設定だったのを11月23日にやることになって「秋の版」に少し変えていただいた。ついては「原子野に秋の花も見えず」などの文言の入れさせてもらったり幾つか私なりの脚色もさせていただいた。能としては教会堂での演能ということでずいぶんいろんな点で冒険をさせてもらっているのでこれは必ず成功させたい。主催者のほうでもだんだん臨戦態勢に入ってきている様子。
次回の稽古は月曜日、新宿御苑の薪能の日、1時より。多田先生もみえる予定。「長崎の聖母」について詳しくはまた書きましょう。
新宿御苑の薪能は、このところ3年ほど雨にたたられ中止が続く。気の毒なり。ずっと前も「大江山」で2年連続中止あり。うちの麻耶と伽耶が子方でよく稽古をしたのに残念だった。今年は去年の番組「翁」と「羽衣」なり。
そして今日の午後は1時より国立の「仏原」(ほとけのはら、シテ浅見真州氏)の申し合わせ。地謡、山本順之氏、若松健史氏、青山よりいっしょに行く。「仏原」は能の中では一般的には「遠い」(―あまり上演されない)が銕仙会では割合「近く」(―時々上演される)、「長崎」とは違って自信持って謡う。「長崎」もそう行こうよ。
笛 藤田大五郎氏、89歳。帰って新聞を見れば文化功労者の一人(長嶋茂雄氏らとともに)。笛を吹くのに、もう息をふーと吹いている様子無し。まさに「名人伝」の世界。今まで恐れ多くてお願いしたことがなかったのだが、来年の第17回
響の会(4月30日(日)、西村氏の「道成寺」)の私の「花月」にお願いしている。よろしくお願いいたします。
申し合わせの後青山に帰ってみれば幸い舞台が空いたので、「高野物狂」を稽古する。そう先日研究公演「花筐」には皆様ご来場有難うございました。(ほんとにこのごろ切符を勧める時間的余裕がなく当日が来てしまう)。
「花筐」と高野」の共通点、大有り。面白い。企画としては最高。しかし実際やるのはなかなか。帰りの電車で思い出したが、昔小学生か中学生だったか、高野山に行ったことがあって、そのとき「三鈷の松」の苗をお土産にした(三鈷の松は高野山のポイント)(私は十歳より東京住まい)。
高野山の薪能で復曲能「刈萱」(シテ大槻文蔵氏)をやったことがあり(NHKでも放映したのでご覧になった方もいらっしゃるか)、私の長男・蓮太郎が子方、私はツレのお母さんの役(当時高野山は女人禁制で麓まできて死んでしまう役)。当日は嵐で、どうにか外で上演できたものの、風で飛ばされそうだった(せりふも飛びそうだった)。その舞台が三鈷の松の前。
観世流の現行「高野物狂」では、結末で主君の子を出家を思いとどまらせて家を継ぐべく故郷へつれて帰るが、他流ではいっしょに高野山で出家してしまう。観世流は近世的。しかし、まあ当日見てみてお客様がどう感じていただけるか。何も筋だけではないから…。30日に響の会の集いで「高野」の研究会あり。そこでもっとイメージを膨らませよう。 |
 |
 |
〔05/10/23〕晴天の快晴の秋晴れの紫式部ホトトギス |
【016】 |
 |
|
 |
この三日間朝早く出かけなくて良くちょっとほっとしている。一昨日はトマトを抜いてウメの枝を切り、山芋のつるをはずしてむかごを取り、昨日は紫式部から山芋のつるをはずしてむかごを取り、今日は朝トイレで新聞を読んでいたらなんと参議院の神奈川の補欠選挙ではないかと知り中学校へ行って選挙を済ませ、グラウンドの野球部の練習をちょっと見ながらまた山芋の蔓を見つけてむかごを摘む。毎日むかごご飯。おいしいのです。
一昨日紫式部には金色の大きな毛虫がいたので遠慮したのだが、帰ったらその毛虫は蟷螂に食べられてしまったと言う。かみさんがみつけて通りかかった近所の子供たちと一部始終を見たという。それならばと昨日紫式部に絡まった蔓を取ったら紫式部が本当に見やすくなって、紫の玉ころが美しい。今朝前を通りかかった人も「鮮やかですね」とほめて通ってくれた。蟷螂はまだいる。
ホトトギス。満開か。どうしてこんな形になるんだろうか。蝶やアブがやってくる。昨日はアゲハもまだ飛んできた。
今日は午後から早稲田の近年の卒業生の稽古。青山倶楽部。せっかく4年間やってずいぶんできるようになったのに、就職してすぐは忙しく遠ざかってしまうのはもったいない、一月に一度でもやろうではないかとしばらく前からはじめたもの。今日は出席少なく、仕舞がシンジロウ「江野島」、パンダさん「杜若クセ」、まりあん「玉の段」、謡が女子「高砂」全曲、そして私がワキでシンジロウがシテで「永訣の朝」全曲を。
「永訣の朝」は京都の青木さん作の新作能。先年私主催で青山の舞台で青木さんにやっていただいたのを是非謡ってみたいとの事で、ここ何回かに分けて稽古をしたもの。(12月3日に京都の青木さんの舞台で蝋燭能として上演予定。地謡に私と西村・柴田両名が参加します)
昨日は岡田君の会。「砧」。私は銕之丞師と後見。砧の作り物の出し入れ。観世流でははじめワキ座に置くのが普通。後に正先に置き換えるのだが、替えの型でツレが橋掛かりでシオッて(泣く型)から幕に入るのを待っていたら間狂言の方が立ってしまったので少しあわてて移動させるというハプニング。ここは申し合わせでやっていなかったのでその旨申し上げておく必要があったかも。
作り物もはじめから正先においておくやり方もあり、今回のように後の途中で引くのもあり最後までおいておくやり方もある。
後の出も大小の鼓による「一声」の囃子で出るのもあり、今回のように太鼓の入った「出端」で出るもあり、またそれも小書(特殊演出)にして「梓」の出端(先日の響の会袴能の折など)で出るもある。装束も大口と言う袴をはいて出るもあり着流しで出るもある。能は決まっているとは言ってもなかなか一様ではない。
終演後、国際交流基金の招聘でメキシコからいらしたカルロス・アシダ氏(カリージョヒル現代美術館 館長)とお会いする。京都へいらっしゃるというので、知らぬ事ながら町屋の再生をご覧になることを推薦する。メキシコでの演能はあまりないのではないだろうか。先々代銕之丞雅雪先生がいらしたときの写真があったと思う。
その前の水曜・木曜の六本木ヒルズ森美術館での「鷹姫」。行き帰りビルの中の経路が大変。案内者無しではなかなか難しい。ニューヨークではきちんと見ることができなかった杉本氏の写真を今回はよく見ることが出来たが、もう一度ゆっくりみたいもの。舞台の成果には是非解決しなければならない課題が残る。またやりましょう。
初日、能の最後近くで地震あり。岩の面をつけていたので誰が揺らしてるんだとはじめ思ったが結構長いのでもしかしたらこれは地震? スーパーエフェクト! 今日は中越地震から一周年。私は何も手助けできなかったけれど、今度2月に西村さんが地元の人たちと復興祈念の能をやってくれる。「羽衣」。皆さんよろしくお願いいたします。
明日は響の会「花筐」の申し合わせ。がんばろう。午後は国士舘の授業へ。そう「羽衣」の本を仕入れなくては…。 |
 |
 |
〔05/10/16〕ラッカヨー 落下よー 落火よー 落果よー 落花よー |
【015】 |
 |
|
 |
今日は船橋で「一石仙人」(11時より申し合わせ、2時開演)。終わってロビーで多田先生が笑顔で暖かい大きな手で握手をしてくださり、ホッとして帰る。(昼の弁当を食べ損なったので青山へ帰る人たちとラーメンを食べて)。
出演者もスタッフの人たちも大変気持ち良くやっていただいて真に有難い。(お客様の少なかったのは残念。)
昨日東洋大学のワークショップを終えて、船橋に入ったら舞台監督から「清水さん、学生さんは?」と言われて「わおー」。オーケストラボックスを上げて舞台を張り出すことになったので学生の助っ人を私が請け負ったのだった。今日が早稲田の学生諸君の舞台があることが分かったのでどうしようかと思っていてそのまま忙しさにまぎれてしまったのだ。申し訳ありません。
舞台監督の寅川チーム、照明の野地チーム、本当に丁寧な仕事をしてくださって有難うございます。10時まで仕込みをやって、皆で一杯呑んで食事をして12時ごろホテルにチェックイン。私はそのままバタンキュウ。
東洋大学のワークショップは昨年に続いて2回目(日本文学文化学科主催)。今回は「天鼓」を取り上げ、まず私が概説と天鼓の前シテの装束を学生のモデルにつけ、能の動きを谷本君に、囃子のことを長山君と囃子方の皆さんにやってもらい、天鼓の後を私が舞いました。井上ホール一杯の人で、2時間半熱心に参加していただいて質問もしっかりとたくさんあり真に有難い。
但し小鼓の人が日にちを間違えてこないことが開演間近に分かり、古賀氏に急遽来てもらうというハプニングあり。(古賀君とは韓国もいっしょでした。去年オランダでもそうフェルメールの絵をいっしょに2時間ほど眺めていました。彼はもともと絵のほうで芸大に行こうと思っていた人です。)
「天鼓」はソウルの芸術大学でもやりました。そちらも熱心ですばらしい催しでした。
韓国の報告をしなければならなかったのですが、帰ってからすばらしいスケヂュールだった(舞台に加えて一石の稽古も長崎の稽古も鷹姫の稽古もあり、またずっと出来なかったお弟子さんの稽古もあり)のでなかなかできず、向こうで少しは書いていたのだけれど今となってはニューヨークと同じく残念ながら「没!」。お世話になった方々有難うございました。多分またお世話になると思います。よろしくお願いいたします。
韓国から帰って後見の役が三つほど続きました。そして全部シテの装束をつけさせていただきました(「三山」万三郎師、「安宅」猶彦氏、「三輪」清和師)。これも有難いこと、自分の後見としての、あるいは装束付けのスタイルを確立していかねばと思います。
そうするうちに木犀は散ってしまいました。あの花たちは「花は根に帰れ」でしょうか、「宇宙の微塵に散らばれ」でしょうか不思議に消えていきます。
「ラッカヨー」。韓国安東市河回村、仮面劇フェスティバルのフィナーレ、川の向こう岸断崖絶壁の上から大松明を落とすのです。こちらの岸から皆で掛け声をかけます。「ラッカヨー」。途中の岩に引っかかって粉々に飛び散るものもあれば、うまく川岸近いところまで落ちて炎を上げるものもあります。豪壮でいてどこか悲しい。嗚呼それは落下であり落火であり落果であり落花であるのでしょう。河回村では150年前の民家に民宿でした。もう一度いきたいと思います。
今日でちょっと一段落です(もちろんまた次にやるべき事がでてくるのですが)。明日の朝はまたむかごを摘みましょう。そして午後は国士舘の授業です。あ、しまった。「羽衣」の本を20冊手配するのを忘れてた。わおー。どうにかしなくっちゃ。 |
 |
 |
〔05/10/5〕金木犀の香・深夜の蚊〈韓国より〉 |
【014】 |
 |
|
 |
今韓国・ソウルのホテル。夕食のあと、西村さんと小寺佐七さんの部屋で過ごしていた。今日のお昼過ぎ、羽田の国際線ターミナルからソウル金浦行の便で無事到着。成田まで行かなくてよいので助かった。
昨日から金木犀が香り始めた。座間市の木が金木犀、そこここでふと香る。
昨夜は小田原の薪能。小田原城の天守閣をバックにしてよいロケーション。朝、東京は雨。午前中、銕仙会での稽古能「砧」(10/22 岡田麗史の会/シテ・岡田麗史)「経正」(10/14
銕仙会定期公演/シテ・若松健史)の最中「(雨だから)これはきっと中だよ」と言っていたら、NHKの録音「野宮」(シテ・山本順之/ワキ・阿部信之/あと、地謡に若松健史、西村高夫、そして小生)のあと確認すると予定通り外での上演との事。ついたら晴れていて、しかし…。蝉も鳴いているし、天守閣の空高くツバメも飛んでいる。舞囃子「自然居士」(榮夫)、狂言「悪坊」(シテ・山本東次郎)のあと休憩をなくして、能「安達原」(シテ・銕之丞/ワキ・宝生閑/私は永島忠侈さんと後見)をはじめ、ワキが出たところでポツポツ。「ありゃ、困ったぞ」。途中、少し止みそうになったけれども、中入前にまた少し強くなってきて、結局シテが中入したところで中止。後見はどうするかの判断をしなければならないので…。雨中シテもワキも囃子方も皆我慢して、中入までやった為か、お客様も素直に帰っていただいたようだ。あらためて薪能開催の大変さを思う。早く終わった分、西村氏と駅前でビールを一杯飲んで帰る。
帰宅したらサンマの塩焼、うまい。冷酒を少々。
響の会WEBにお客様から寄せられた装束に関する質問にメールでお答えしたりして、寝入ってしばらくして「ブ〜ン」。3時半頃、一匹首尾良くやっつけて電気を消してしばらくしたらまた「ブ〜ン」。今度はなかなか発見できず、やむなく、蚊取り線香を焚く。うちの豚は「紅の豚」のあれ。また電気を消したら今度は電話が鳴る。コレクトコール。心当たりがないので切る。そしてもう一度、ウ〜。しばらく眼がさめていたが、いつしか…。あっと思ったら、ワァ、6時20分。ソフトボール娘のための弁当作りの助手。そうだ、空手ネエサン(一昨日アゴやクチビルをひどく腫らして帰ってきた。電車でとなりの人がギョッとするだろう。DVじゃないよ)がパン屋のアルバイトに6時30分に出ると言ってた? 駅まで乗っていった自転車を雨中取りに行く。道すがら金木犀の甘い香り。一眠りして荷物を作って出かける。
ああ、今日は成田じゃなくてよかった。 |
 |
 |
〔05/10/2〕国勢調査とむかごの収穫 |
【013】 |
 |
|
 |
今日は久しぶりに全日休み。(西村さんの花筐の銕之丞師による稽古が夕方からあるのだがなかなか東京まで行く元気が今日はなく所謂自主休講。すみません。)10月に入ったというのにせみが鳴く。真夏日か。午前も午後もお昼寝。日が翳ってきて庭の山芋のむかごを摘む。まだ小さいのは残して、今年はまあまあ。ウメやモッコクやトマトやいろいろに這い絡んだつるからざるに収穫する。売るほどはもちろんないが、今夜のむかごご飯や酒の肴程度にはなりそう。
旅行や舞台が終わって部屋が散らかってそのまま次に移っていく状態が続いて、足の踏み場がだんだんなくなって、今日はそれをかたずける良い機会だったのだったけれども、もう日はとっぷりと暮れて、気はすでに明日の朝の一石仙人の稽古に移っていく。
ニューヨークからの帰りの飛行機で日記を原稿用紙にたくさん書いたのだけれども、もう打ち込む余裕はないので「しみかん日記 9.28 高度37000FEET 対地速度582MPH 外気温−62°F」は残念ながら没。国勢調査では9.24から9.30までの労働時間を書く欄があったが、これはなんとも書きようがないのでとりあえず70時間に。
ニューヨーク帰りに我が家で迎えてくれたのは、大輪の夕顔一輪。昨日も一輪。後もう一輪くらい咲くか。水引も永いねよく咲いてる。紫蘇の穂がたくさん出てかわいい白い花(お刺身にいいね)。紫式部の玉ころが紫に染まってきました。
さあ10月。体をいたわりつつ、自分の舞台の課題をクリアーしていきましょう。 |
 |
|
 |
|