|
|
 |
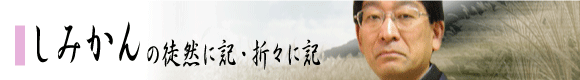 |
 |
 |
|
|
 |
 |
〔06/12/29〕急いで浄土を願うべし なもうだ なもうだ |
【106】 |
 |
|
 |
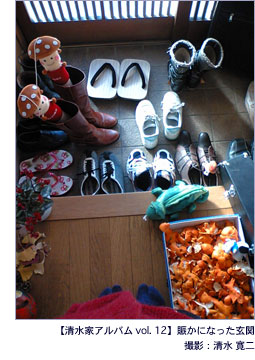 今夜は骨付き唐揚。昨日帰ってきたソフト娘のリクエスト。マンドリン娘(サークルでのニックネームはなぜか「いえやす」らしい)も昨日大阪から帰省。一挙に人口増える。唐揚36本。ジャガイモとレンコンも揚げる。レンコンはかみさんの郷里佐賀、白石からのものだが(この前の暑さに少しやられてはいたが)、うまいよ、やっぱり。 今夜は骨付き唐揚。昨日帰ってきたソフト娘のリクエスト。マンドリン娘(サークルでのニックネームはなぜか「いえやす」らしい)も昨日大阪から帰省。一挙に人口増える。唐揚36本。ジャガイモとレンコンも揚げる。レンコンはかみさんの郷里佐賀、白石からのものだが(この前の暑さに少しやられてはいたが)、うまいよ、やっぱり。
一昨日か、年末に20度はおかしいよ。しかしそのおかげで、その日宝生閑家の餅つきは寒くなくてよかった。このところ毎年かみさんと伺っている。もう搗くんじゃないよと言われて行ったが、行って搗かないわけにはいかないよ。一臼につき一回(20余搗きくらい?)ずつ。しかしやってみると以外に楽なんだ。おお毎年やっている甲斐あるか。でもまあ一回ずつだからね。一緒にいると、彼ら下掛宝生流若手の舞台の良さがよくわかる。実に自分の出処進退が分かっていてきちんと「受けて」いるんだ。閑先生はじめ皆さん来年もよろしくお願いいたします。
かみさんは丸め手。今回は丸め手に新橋の若手お姉さんが二人。しばらくご無沙汰しています。今度また是非・・・。
クリスマスイブに萌の会で謡った南無阿弥陀仏「鉢叩き唄」がようやく頭の中から少し離れてきた。イブに南無阿弥陀仏! この曲は実は、前から謡ってみたかった。ほんの一部だけど実現。しかも萬先生の導師!この前先代万蔵(耕介氏)追善のときに能〈輪蔵〉の間としてあったが、そのとき後で萬先生は「今日のは陽で、私はやはり陰の方が・・・。」とおっしゃっていた。ハハ、しかし私たちの謡ったのは陰とも陽とも、もちろんただ歌っただけのもの。早歌や能の小歌をいくつか構成した〈狂言遊宴〉。どれだけ生活の中に「舞歌の二曲」を取り込んで役者として生活しているか。まずは楽しくはありましたが、厳しく、そして悲しい試みでした。
その前の日は「至高の華」という催し、一部二部で梅若六郎氏のシテ二曲、〈松風〉と〈鵺〉。私は両方後見。なかなかうまくいかない。えい、また頑張るにゃん。
昨日から手帳は空欄。大掃除といきたいところだけど、体がそうは動かない。まあぼちぼち出来るところから少し。仏様のあたりだけは拭き掃除する。ああ、そこだけ輝いてる。
来年の響の会の番組の細部が決まってきた。三役は決定。地謡後見の案を西村さんにファックスする。
研究公演の狂言の人は決まってきたけれど曲目がまだ。乞うご期待。
九月の響の会は、野村万作師の〈箕被〉。連歌に興じて上で、女房を離縁しなければならなくなった男。これはとてもいい狂言。(おかげでこの日はいい番組になった。)
一昨日夜は渡邊守章氏の訳書「繻子の靴」(クローデル)による毎日出版文化賞と日本翻訳文化賞受賞を祝っての能関係の集まり(万作氏も出席)で、いろいろ面白い話は出たが(小鼓の北村治氏―早稲田の仏文出身―と渡邊先生との掛合いはなかなか面白い。)、連歌の話も。ほんとに話が連なる。
今日午後、〈野宮〉を一曲謡っていたら(ちょうど61分、少し重いか)、フト浮かんだことあり。先日の法政のシンポジウムから渡邊守章先生、そして連歌等が一線に並んだもの。これは九月の「野宮」の前に銕仙会の舞台を使って是非実現したい。乞うご期待。
その〈野宮〉のワキ「いと艶めける女性一人忽然と来り給うは如何なる人にてましますぞ」のところで、庭の榊に緑色の鳥来る見ゆ。シテ「如何なる者ぞと問わせ給ふ。そなたをこそ・・・。」 ああ、メジロだ。おお、おいしそうな、うぐいすもちか。しばらく飛び廻って、やがて飛び去りぬ。
ワキ「今持ち給う賢木(榊)の枝も昔に変わらぬ色よなう」 シテ「昔に変らぬ色ぞとは。榊のみこそ常盤の蔭の」 ワキ「紅葉かつ散り」・・・
今出ているサライのインタビュウが野村万作氏。〈釣狐〉のことなどを中心にして、よく聞いている。やはり万作先生は真摯だ。
私も今出ているアエラ・イングリッシュに能の記事があって、それに出ている。見開きだけの短いものだが、今年は、いくつかのワークショップや解説などでずいぶん勉強させてもらった、それが短い中ではあるが反映できたか。いつかもっと長いものをね。
さて来年11月ボストンでの〈一石仙人〉公演の話が進んでいる。イングリッシュもやらなくちゃ。(ラーストリーフのことから、石丸先生の話等、あといくつか書きとめておきたいことあれどまた今夜もこの辺で)Good
night!
そうだこの!(ビックリ、オッタマゲーション)マークについて書くべきことあり。今度ね。 |
 |
 |
〔06/12/26〕秋の花 皆衰えて 赤鼻も去り 仕事収め |
【105】 |
 |
|
 |
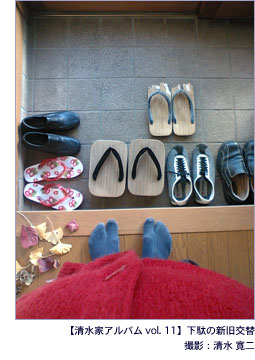 今日(座間の稽古)で今年の公式な仕事は終わり。お疲れ様でした。このところ最後の山で、あるいは秋の疲れも出たのか、この日記も書けず、まことに久しぶり。ほんとに忙しさの山の時は書くことも山とあるのにもったいない、書けずに終わってしまうのだ。所詮この世は無常なり。 今日(座間の稽古)で今年の公式な仕事は終わり。お疲れ様でした。このところ最後の山で、あるいは秋の疲れも出たのか、この日記も書けず、まことに久しぶり。ほんとに忙しさの山の時は書くことも山とあるのにもったいない、書けずに終わってしまうのだ。所詮この世は無常なり。
今日は夕方から風雨強く、「山より出る北時雨」(定家)どころでなくもうだんだん嵐、さっきから雷もひどく、子供たちよ早く帰れかし。
◎前回の日記以降書くべきこと(1)
法政の能の翻訳に関するシンポジウム。三日間のうち二日目丸まると三日目の午前中参加。面白かったー。疲労感の中行った甲斐あり、これから能をやっていくについてある側面が開けた感あり。つい手を上げて質問したり、感想を述べたり。〈一石仙人〉アメリカ公演にも力を得たが、ことに来年響の会にて〈野宮〉をやる“気”を貰った。(当初〈江口〉と思っていたのを、銕仙会の番組と重なり〈野宮〉に変更したが、正直なところ、さてこの大変な能をどこからやっていこうかと思っていた。)
うちの庭も〈野宮〉にあるように「秋の花皆衰えて・・・」。菊も色を変じてほとんど切ってしまったし、三つ残っていたトマトも抜いたし、カマチャンもどこかへ行ってしまった。(シソの茂っていたところには一箱頂いた下仁田ネギを活けてある。)しかし、花は実は絶えない。今度は冬の花が咲き出している。ピンクのバラさんが咲いているし(アリャ明日の朝見たら今夜の嵐にもう散っているかも)、水仙もモッコクの下に咲き出した。南天の赤い葉も色を添えている。榊も花の蕾をつけてきた。「身にしむ色の消えかえり・・・」。
〈野宮〉=金春禅竹作。禅竹の翻訳の発表はワシントン大学シアトル校のポール・S・アトキンス助教授(かつて銕仙会もよくご覧になっていたという)。
シテ 折りしもあれ物のさみしき秋暮れて
Now the lonely autumn draws to a close:
なほ萎り行く袖の露
dew upon sleeves that wilt even further,
身を砕くなる夕まぐれ
this twilight that shatters the self.
心の色はおのづから
The colors of the heart have of themselves
千種の花に移ろひて
appeared in the blossoms of the various grasses;
衰ふる身の慣らひかな
such is the custom of decay.
 当日の資料より勝手に転載させていただきました。(ただし一行ずつ合わせてみました。)今度是非シアトルまでうかがいます。 当日の資料より勝手に転載させていただきました。(ただし一行ずつ合わせてみました。)今度是非シアトルまでうかがいます。
野宮で思い出すのは、いつか新潟のほうで橋の会が〈紫の上〉をやったときのシンポジウムで、丸谷才一氏が「賢木の巻では『実事があった』と考えるのが自然だ。」とおっしゃったこと。
「かくて君ここに、詣でさせ給ひつつ、情をかけて様々の、言葉の露も・・・」
「景色も仮なる小柴垣、露うち払ひ、訪はれし我もその人も、ただ夢の夜と経り行く跡なるに・・・、懐かしや〔破之舞〕」
ほかにも法政での事、書くべきこと多けれど詳細はまた書く時を得て。
はや夜も更けたり。
先ほど空手娘も駅からタクシーにてご帰還なり(一番ひどいときだったか)、そしてもう寝てしまった。
雷もはや去ったか。おお、私も目がしょぼしょぼ。はっはっは、(面にかぶれて)鼻の赤くなっていたのは、クリスマスも終わったので取れてきたぞい。
ではGood night! |
 |
|
 |
|