|
|
 |
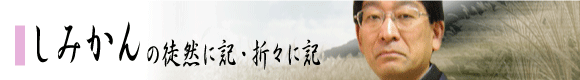 |
 |
 |
〔07/01/31〕大山上空ダイヤモンドの一番星発見 |
【110】 |
 |
|
 |
今夜はてんぷら。
まず大和芋のすったのに少しカニを混ぜて海苔で包んで揚げた物。それから庭のフキノトウ(いい香り、あったかいからもう花になっちゃうよ)。ジャガイモ。野菜スープで煮込んだ煮豚の味噌焼きを切って揚げた物。玉葱(これは北海道産か、かあちゃんはやっぱり佐賀のがおいしいと言う)。最後に「ワラスボ(有明海の怪魚の干物)」! みんな売り物になるよ。
それとカニ缶のカニのねぎ・しょうゆマヨネーズ和え。イカの塩辛。
味噌汁は古典的に豆腐、あぶらげ、ネギ。
また飲みすぎちゃうよ。(昨日は昼間から神田の藪にて、節分の「おばけの相談」と称して、新橋への出勤前であまり飲まない人も混ぜて四人でお銚子16本!)
うちもだんだん人口が減ったので、食事の仕込み方を変えなくてはならない。
今朝また一人出て行った。
空手娘がアルバイトだった歯医者さんにこの前から正社員として採用になり(初給料で買ってきたケーキになんだかごまかされたような・・・)、池袋の先の要町にアパートを借りて(空手の道場と職場への便を考えたらしい。昨日江古田にお住まいの閑先生によろしくと言っておいたよ。)、独立となった次第。この前「もう決めてきたから、契約書にサインして。」
今朝7時のあわただしい出勤のお出かけに「お世話になりました」。切り火を切って出してやる。ああ、しかしまだ忘れ物やら整理し切れてないものやら。おや、パスポート置いてあるぞ!
あと残るは蓮太郎。修士論文の締め切り迫って毎日終電間際。まあ手伝えるのは「飯食ったか?」と聞くことぐらいだ。地下深いところで生成されるダイヤモンドのことを書いているらしい。おきばりやす。今夜は星がダイヤモンドのようだよ。 |
 |
 |
〔07/01/21〕大寒の鶉舞 センター試験には雪 |
【109】 |
 |
|
 |
今朝は穏やか。玄関のシュンランに蕾発見。ホトケノザも咲いている。フキノトウもふくらんできた。ウメの蕾も、サカキの蕾も。ああ、大山のてっぺんは白い。丹沢の奥山はもっと白い。でも今日の受験生は大丈夫。
昨日は大寒。センター試験だし、まさかまた雪は降らないよねと言って障子を開けたら、アリャ白いものがチラチラ。
長男蓮太郎の時もずいぶん降って、向ヶ丘遊園の専修大学が会場だったのだがその坂で滑って(アリャ不穏当。名誉のために言えば東工大受かったんだよ。)転んだといっていた。電車が遅れたときもあったし、受験生には♪「ゆ〜きのふる街をー」などと歌っている余裕はないよね。まあ今日はそうは降らないか、ああしかし〈木六駄〉日和だ、と国立の「萬狂言 冬公演」へ出かける。
野村萬先生の喜寿のお祝いの会。ご自身の〈庵の梅〉と〈木六駄〉。
私は〈庵の梅〉のおシテ萬先生の装束着付けのお手伝い。唐織を姥付け(うばづけ―唐織は現在花頭(かとう)、あるいは熨斗(のし)と言って襟を外に立てて着るやり方が着流しの時普通だが(昔の絵ではそうではない)、水衣を上に着るときや姥の役などは襟を巻いて小袖風に着る、そのやり方。狂言の小袖の着付けでは細い帯をしているが、この姥付けでは唐織紐という細い組みひも一本で〆て帯や紐は見えない)に着て花帽子。姥の面は新作狂言〈楢山節考〉(1957年)のときおりんさん用に作ったものとのこと。
とてもいい唐織(赤が褪めてまことに上品、老女にもってこい)、貰って帰りたいくらいだったが寸法は萬先生にツイタケ。丸々後ろのヒモは見えていた。しかも老女の構えで、大分窮屈だったろうが、さすがにきちんと着こなしておられた。
花帽子が曲者。なかなか上手くいかないのだが、どうやら。もうちょっと工夫も出来たかと思うが、喜寿のお祝いに免じて77点くらいにしておいて下さい。
〈庵の梅〉は若い女房たちと歌や小唄、舞のやり取り。紅白の梅の作り物も出て、なかなかほのぼのとして品格があって素晴らしい狂言であった。曲中「ああ、雅味があって、とても耳にいい言葉だな」と言う言葉いくつもあり。素敵です。
〈木六駄〉は雪の狂言。丹波から雪の老の坂の峠を越えて都へ12頭の牛を追うて行く。
地裏で拝見しながら雪の能〈鉢木〉がやりたいナなどとも思う。へへ、この〈木六駄)もやってみたいよねー。「ちょう、ちょう、させい、ほーせい!」―橋掛かりから舞台まで縦横に使って雪中の細い峠道を牛を追って行く狂言の演技の素晴らしさ。茶屋で飲む酒に温まっていく様。(そう言えば学生時代に父君六世万蔵氏の〈木六駄〉の舞台も拝見したと思うが、そのフィルムを何回も見たね。萬先生もパンフレットの父君のことを書いておられる。)
かつて私のやっていた地照舎の催しで八世万蔵(耕介)氏にこの〈木六駄〉をやってもらったことが有る。(〈木六駄〉と私の〈大江山〉の組み合わせ。)
その時は彼が初演で、曲中老の坂の茶屋での酒盛りに舞う小舞が、初演のときは〈鶉舞〉はやってはいけないことになっているとのことで、確か〈柳の下〉であった。やっぱり〈木六駄〉には〈鶉舞〉。でもこれは小舞ではないね、いわば大舞。いつかその〈鶉舞〉で〈木六駄〉をといっていたのだが、彼はもう逝ってしまった。
その耕介の子息太一郎君(90年生まれ)の語り〈那須与一語〉の披き(習い物を初演する事)有。途中で扇の骨が外れるハプニング有。しかし彼は直球でやりきった。よし!
これから祖父萬、叔父万蔵の相手役としても出てこよう。待ってるよ。お母さんも一安心なるべし。
もともとあいていた日なのに、いい日になった。帰りのロマンスカー、「あんなに美味そうに(お酒を)飲まれちゃナ」などと、新宿駅のカフェで生ビールのカップを仕込んで乗る。相武台の駅のスーパーでは「パンだけ買ってきてね。」と言われたのに、ハハハ、長崎のタコも買って帰る。まこと「酔仙」・・・の純米常温なり(すなわち一升瓶から)。
さてこの昼からは広島(平和公園スタート。広島でいつか是非〈一石仙人〉を)での都道府県対抗駅伝のラヂオ放送。三区で早稲田の竹澤君が(兵庫県代表)一位でたすきを渡す。箱根駅伝でも頑張ったね。今年早稲田は箱根、十位内でどうやらシード権獲得。
箱根のときは(ラヂオ観戦にて)もちろん母校、蓮太郎やソフト娘の早稲田・空手娘の国学院、私の今教えている国士舘も応援したが、「東洋」と「白石」も応援。東洋大学は去年まで三年続けてワークショップで伺って(今年は何かテーマを決めましょう)、なんだか近親感あり。ちょうど間のいい順位で放送であんまり出てこなかったが頑張ったよね。うちのかみさんの出身校、佐賀の白石高校はもちろん直接出ているわけではないんだが、その卒業生が優勝校順天堂のアンカー君など各大学に散らばって頑張っていた。
さてあいだに昼ごはん、肉団子汁の残りでおやじのオジヤ!
このところ日記、間があいた。その間に銕仙会の初会やら各稽古場の初稽古やら、そしてわが誕生日有。54歳。師観世寿夫は53歳にして逝けり。ほい、もちろん私は私でしかない。今年も舞台のハードルは高く設定されている。なかなかお金には縁がないんだけれど、心の余裕を持って豊かな言語生活を送っていきたいね。改めて今年の目標を。
駅伝は兵庫県が優勝。三位に佐賀県! 奈良県、沖縄県が30何番目か。両方とも頑張ったね、特に今まで毎年最下位の方にいた沖縄県。今度また2月に沖縄県立芸大の集中講義に参ります。(明日は国士舘で今年度最後の授業。先週はサシコミ・ヒラキ・左右の試験。明日は〈羽衣〉の装束付けを見せる予定。)今度は宿泊一日伸ばして、「ユタ」のことも調べます。なぜ調べるか、詳細はやがて。学生諸君、先生方よろしくお願いいたします。
兵庫県は幼少の砌(十歳まで)住まい致していた所なり。淡路島の江崎灯台に神戸市の何箇所か。しかし、先の大震災に私は何も動くことが出来なかった。
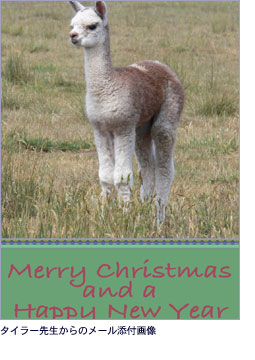 奈良県は長くは住んでいないが、私の生まれたふるさと。そう、ロイヤル・タイラー先生(日本語で書くと「平皇家」?)の法政のシンポジウムのときの記事が写真付で一月遅れの18日の朝日の夕刊に出ていた(山本健一氏の記事)。先日タイラー先生からメールを頂戴したら(アルパカの写真付)、確かに私の地照舎での〈葛城〉を見ていただいていたが、そのころ奈良のあちこちを歩かれて、金剛山にもご夫妻で登られたそうだ。金剛山の麓が私の生まれた故里、葛城の里。雪降っているかな。 奈良県は長くは住んでいないが、私の生まれたふるさと。そう、ロイヤル・タイラー先生(日本語で書くと「平皇家」?)の法政のシンポジウムのときの記事が写真付で一月遅れの18日の朝日の夕刊に出ていた(山本健一氏の記事)。先日タイラー先生からメールを頂戴したら(アルパカの写真付)、確かに私の地照舎での〈葛城〉を見ていただいていたが、そのころ奈良のあちこちを歩かれて、金剛山にもご夫妻で登られたそうだ。金剛山の麓が私の生まれた故里、葛城の里。雪降っているかな。
この前積み上がってちっとも整理できない物どもをちょっと開いてみれば地照舎のパンフレット類。大江山や葛城。今度ご紹介しよう。
さて、ちょっと散歩に行くか。 |
 |
 |
〔07/01/08〕念仏バイリンガルあったかーい |
【108】 |
 |
|
 |
今日は成人式とかや。15日でないとそんな気がしない。はや新年も一週間過ぎたとかや。オウ、もう今年も五十分の一が終わってしまったか。それにしても暖かい。
朝のかみさんの念仏「なまんだぶ、なまんだぶ・・・」(かみさんの親父さんは95歳か。もう娘が行っても「誰じゃったろう?」と言うくらいだが、朝晩のお念仏は欠かさない)。
あれ、この前近くの宗仲寺へ年始参りに行った時は(3日の午後で誰もいない本堂、ご本尊の前でマンドリン娘と三人で同称十念。遠くから座間神社の鐘とアメリカ軍のジェット戦闘機の音。)、たしか「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏・・・」と言っていたぞ。
オウ、念仏バイリンガル。
南無阿弥陀仏に引かれて〈当麻〉を謡う。65分ほどか。重い? この間にかみさんは買い物に行ってきた。お昼はぺペロンチーノ(そうかイタリア人は毎日イタリア料理か)。
昨日は三時に食べた金沢の森八のお菓子「山里」に引かれて〈大原御幸〉を謡う。シテの謡い始めが「山里は・・・」。これは75分を超えた。ハハハ、重いか。
〈大原御幸〉で思い出すのはやっぱり、平泉中尊寺でのもの。粟谷菊生先生が異流共演で「法皇」だった。(シテ先代銕之丞、ツレの内侍が私、局が西村さん)
うちの清門会が青山で定期的にやるようになった始めの時に、番外で素謡の〈大原御幸〉を出した。これもシテ先代銕之丞。一生懸命謡っていただきました。来年20回記念にも何かの形で出したい曲。
昨日の朝は〈舎利〉を謡う。今度明治座にて片山清司氏の能あり。(二月の銕仙会でもあり。)私は地謡だが、アリャリャン、忘れてるねえ。
どうしてこのワキは出雲から来るのかねえ。舎利を足疾鬼が取って行くところ、ワキの夢かもね。だからシテは「俺がやるんだ。」なんてやっちゃいけないんだね。まあ何の能でもそうだね。
昨日、去年暮れの法政の「能の翻訳を考える」というシンポジウムで特別講演をなさったロイヤル・タイラー先生にメールを。緊張。あの時〈井筒〉の後だったせいもあるのかとても感動して、色々質問したり感想を述べたりしてしまった。にもかかわらずその中心であったタイラー先生に空いた時間にご挨拶もせず稽古へバックレテしまったので、あの研究会の責任者であった山中女史へのメールに「あやつは何者じゃ」とのこと。しかも1995年私がやった地照舎の〈葛城〉をご覧になっていたらしいのである。まことに恐れ多いことなりと、英語では無理なのでまったく日本語でメールを。私の質問にお答えになる先生のお顔がありありと浮かんできます。今後ともよろしくお願いいたします。
今夜はすき焼き。金粉入り日本酒。
今年に入って一日・五日・六日と日本酒をしこたま飲む機会アリ(二日酔無)。
1日、赤坂の「卯佐木」にて榮夫先生の新年会。(田無の親父とお袋を訪ねてからまわる。なかなか行けないから今年もゆっくり元気でね。)
5日は青山銕仙会にて観世銕之丞家の謡初、引き続いて新年会。四時からが、終電にて帰宅。今年は少し出席者少なかったが―それでも地謡座に15,6人か―、謡初の緊張感、毎年ながらいいもんです。後の新年会はうどんすきにて。ここでの会話も大事。最後に残ったテーブルにて「やっぱり能で大事なのは地謡!」。力強い囃子方の先輩の発言。
謡初の曲目は毎年同じ「老松」「東北」「高砂」、これは江戸城中の謡初に同じ。前日にうちで蓮太郎と同じところを予行演習。君ちゃんと謡えるじゃん。)
6日は某先生のお招きで上野の「むらた」にて(前日決まった)。
まことにご馳走様です。おいしく頂戴いたしました。女将さんが「お銚子の底が抜けたのかしらねえ」。アリャ全部榮夫先生とご一緒なり。いろんなお話を伺いました。「清水君は謡がだめだ」・・・。先生、今年は80歳です卯ね、どうぞ今年もお元気で。
「むらた」で、清水先生の奥様のファンになってしまいましたという若いおねえさん二人。おお、暮れのお餅つきの丸め方。ちぎって丸めるのが上手かったのね。佐賀弁も上手いよ。このバイリンガルを新橋で雇っていただこうか。
南無阿弥陀仏。暮れに大阪の私のいとこが身罷った。45歳。
狂言遊宴での「鉢叩歌」の一節。
「あれを見よ、鳥辺の山に立つ煙、立ちつづけても、立たぬ日もなし。
あだし野の、露ははかなきたとへなり、露にも劣る、人の命ぞ。
思えば浮世は夢の世ぞかし、・・・急いで浄土を願うべし
なもうだ、なもうだ、・・・南無阿弥だんぶや、なもうだ、波羅蜜、はっぱいぽう!」
明日は稽古能。新年会での現銕之丞師、「稽古能をきっちりやり続けることが大事だと思っている」。今年もよろしくお願いいたします。 |
 |
|
 |
|