|
白い菊に囲まれて菊生先生の笑顔のお写真。「大好きな菊生さん、さようなら」。今日は粟谷菊生先生の葬儀(増上寺にて)。友人代表としての野村萬先生の弔辞。今スーツはこれしかないのに涙が一筋しみを作る。
行きは地下鉄(都営大江戸線大門駅)で順之さんと一緒になる。帰りは若松さんと新宿まで一緒。今週土曜日の国立の〈井筒〉はシテ山本順之、地頭若松健史のコンビ。私と西村が若松さんの隣で謡う。
駅までは宝生流の今井泰男先生とも御一緒。菊生先生よりひとつ上(1921年生まれ)。「面白いのがだんだんいなくなるよ。楽したらだめだから電車で。午前中に文化財で〈安宅〉を一人で全曲録音して来たよ。(お酒も毎日ですか?)録音の2,3日前はやめるよ。」4年で100曲録音の途中とのこと。地下鉄に乗る私たちと別れて浜松町のほうへテクテク。もしかしたら能を舞っているシテ方最長老か。野村又三郎さん(お元気なお姿を見かける)と同年とか。
弔辞のそれぞれや、先人たちのお姿、そして喪主明生さんの挨拶にあったこれからももっと能をやっていく決意に元気をもらって帰る。楽しく元気に厳しくやろうよ。
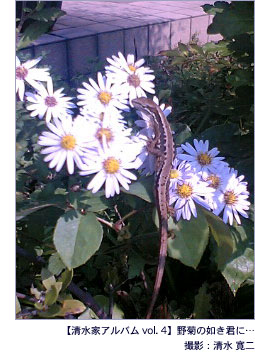 うちの駅の本屋によって週刊朝日百科の『週刊人間国宝』の「24号・能楽(1)」と「25号・能楽(2)」のシテ方特集を買って帰る。出たばかりの「25号・能楽(2)」は菊生先生が表紙。「24号・能楽(1)」に先代銕之丞先生〈定家〉の写真があるがこの長絹は私と西村氏で持っているもの。この前鵜澤久さんが〈卒塔婆小町〉に使用。) うちの駅の本屋によって週刊朝日百科の『週刊人間国宝』の「24号・能楽(1)」と「25号・能楽(2)」のシテ方特集を買って帰る。出たばかりの「25号・能楽(2)」は菊生先生が表紙。「24号・能楽(1)」に先代銕之丞先生〈定家〉の写真があるがこの長絹は私と西村氏で持っているもの。この前鵜澤久さんが〈卒塔婆小町〉に使用。)
桜間道雄師や後藤得三師は私の学生時代に関東観世流能楽連盟の鑑賞能に出ていただいて座談会でお話も伺った。このことなどはいつか書こう。
おお明日はもう立冬とか。
ずっと色々あって、書けない時ほど書くことは一杯あるということで、残しておけないことは残念。
一行づつでも思い出して書いてみるか。
●〔06/11/06〕 国士舘授業。復習と先の羽衣キリの謡やってみる。小田急線鶴川からバスだがバス停の近くで山芋のむかご少々収穫。この辺は広袴(ひろはかま)という地名。狂言の山本則俊さん一家がお住まい。能が谷というのもあるがこれはあの白洲正子さんが住んだから?あるいは地名に惹かれて引っ越したのか?
●〔06/11/05〕 銕仙会にてベケットの催し。例の〈クァッド〉(但し早稲田の時より短縮版で)。アイルランドからの役者さんたちはやっぱりいいね。英語でやってるし。打上げはやっぱりギネス!アイルランド大使館のこの担当の女性はいつかの私たちのダブリンでの公演を観てくれていたらしい。今度はこれを是非ダブリンで。
●〔06/11/04〕 座間の薪能。朝から舞台設営を手伝う。開演40分前に雷雨! ホールへ急遽移動。ああ近くでよかった。しかしもう大丈夫だろうと職員の方々に帰ってもらった後だったので照明等大変だったが、ともかく20分遅れで開演。役者もスタッフもお客様も皆様お疲れ様。私〈清経〉のシテをいくつかミス。こら実力足りないぞ!
 ●〔06/11/03〕 銕仙会にて『清門会』。10時から6時半すぎ。仕舞二つと独吟何番かを除いて全部出る。昼を食べる暇も有らばこそ。お茶も入れてくれるんだが飲まずに出てしまったり。みんな点数良かった。能も2番、〈楊貴妃〉(今度80歳)と〈海士〉。向きが違ったりした時もあったけれど舞い通した力はたいしたもの。またやりましょう。お疲れ様。打上げはフロラシオン。よさそうなものが出ていたがまたあんまり食べずに(明日のものがたくさんあるので蓮太郎とタクシーで帰る)帰ってから弁当食べる。 ●〔06/11/03〕 銕仙会にて『清門会』。10時から6時半すぎ。仕舞二つと独吟何番かを除いて全部出る。昼を食べる暇も有らばこそ。お茶も入れてくれるんだが飲まずに出てしまったり。みんな点数良かった。能も2番、〈楊貴妃〉(今度80歳)と〈海士〉。向きが違ったりした時もあったけれど舞い通した力はたいしたもの。またやりましょう。お疲れ様。打上げはフロラシオン。よさそうなものが出ていたがまたあんまり食べずに(明日のものがたくさんあるので蓮太郎とタクシーで帰る)帰ってから弁当食べる。
●〔06/11/02〕 休日の予定だったが少し明日のための補習。終わって帰ろうと地下鉄への道で一人やってくるのに遭遇。ありゃもう遅いよ、明日頑張って。
●〔06/11/01〕 三菱さん稽古。明後日、うーんうまくいきそうな、心配な・・・。
●〔06/10/31〕 稽古能〈自然居士〉・〈女郎花〉。来月の銕仙会のもの。〈自然居士〉は地を謡い、〈女郎花〉は後見として(この曲は舞台上で特別後見の仕事は無い)ワキを謡う。それからベケットの稽古。それから西村氏と響の会のDM発送作業。昨日大久保・平尾委員が宛名のラベルを貼り通信とチラシを入れてくれておいてくれたものに挨拶と銕仙会の来年の年間番組を入れて封。銕仙会の藤岡さんも手伝ってくれる。(こうした時にフト普段思っていることが言えるもの。いろいろ改善したいことがあるんだよね。)黒猫メールの回収に間に合う。終わって帰りに西村さんと地下鉄の駅の蕎麦屋(コンコースの一番端にあり)でちょっと一杯。が、ちょっと長くなって・・・。
●〔06/10/30〕 清門会の申し合わせ。10時半より。能の申し合わせ普通素人の人のは装束をつけること多いが、私は当日たとえ多少見当は違ってもつけないでと思っている。まずまずうまくいって、早稲田の学生たちの秋季公演へ走る。4時から予定の舞囃子〈竹生島〉だけは見る約束。矢来能楽堂。5分前に着き、元気に出来たことを見届けて再び青山へ。ようやくお昼を食べてあと謡や仕舞など。
●〔06/10/29〕 ここは書いたか。(こちら→)
●〔06/10/28〕 歯医者。今度は12月でよいとのこと。空手のパン屋娘がなんだか白山の歯医者さんに就職。空手の道場に近いが理由。午後富士高の同期会。昨日と同じ東銀座。100人ほどの出席。(この春の響の会を見ていただいた秩父先生も。94歳!)はじめに私の能の話ということで開演前から司会の某君に羽衣の装束をつけ始める。(人手と予算があれば誰か連れてきて私につけてもらって何かやっても良かったんだが・・・。)話は簡単に羽衣から能の魅力。そして羽衣のキリを自分で謡って舞う。久しぶりのメンバー(先生方があまり変わってなかったり、あれあんな先生いたっけと思ったら白髪の生徒、また訃報もあり)、いろいろ趣向もあり1次会だけで4時間。数寄屋橋近くでの2次会まで。わが母校泰明小学校もまだあるね。
●〔06/10/27〕 亀井兄弟の三響会(新橋演舞場、昼夜二部)。この3人とは子方からの付き合い。囃子事や歌舞伎そして能。能は〈安達原〉(シテ観世喜正氏と片山清司氏)。私は後見。花道も使う。朝10時半から場当り。終演、演舞場を出たらもう夜10時。
●〔06/10/26〕 全日本音楽教育研究会高等学校部会全国大会(於横浜メルパルク)にてワークショップのうちの一つを担当。ちょうど今朝の朝日新聞(しばらく前に夕刊の一面にお相撲の特集連載をやっていたが、あれを書いていたのは早稲田の観世会の後輩、横浜っ子)の朝刊に高橋睦郎氏が〈天鼓〉のことを書いていたのでそれを導入にする(人を愛する心、音楽を愛する心)。高橋氏が引用したキリの部分を私が謡う。ここに強吟から弱吟への転調部分あり、そこから音階の話へ。参加者には正座をしてもらって羽衣の部分を謡ってみる。そして構えと運びも。そして少しだが立って謡ってみる。もともと押していたので終わってもとの控室へよらずに(幹事の先生方に挨拶もせず)、国立能楽堂へ急ぐ。〈蝉丸〉。3夜連続の中日。今日は「逆髪」が梅若六郎師、「蝉丸」が観世清和師、地頭が銕之丞師(私はその左側で地を謡う)。逆髪の「緋の長袴」に「モギ胴」姿(上着を着けない着付けだけの姿のこと)の大迫力。普通にない?異様さ。
うーん夜も更けたり。朝刊も来た(ここらは印刷所が近いとかで早いのだ)。この辺でお休みとしよう。一行と言ったのについつい・・・。しかし何をやったか書いてるだけではやっぱりだめですな。季節が動いているよね。菊が株毎に違う色を見せてくれている。それらを日々に!
今朝は大変な風だった。自転車は倒れるし、どこかでは竜巻だったらしい。シソの穂もそろそろあと少しで終わりか。この前座間の薪能の時、浅見慈一君が装束を取りに来てくれて(会場まで歩いて2,3分か)シソを見つけ感心していたので、穂を採ってあげたらパクリ!今日、種をとったので今度あげよう。代々木の舞台の庭にまいてみてください。紫蘇の森に蟷螂発見.さて蟷螂の出てくる能はいずれぞ。この前杉並能楽堂で稽古していたら見所に出てきたので、早稲田の学生たちには聞いたので、彼らはわかっている。はず・・・。
|