|
|
 |
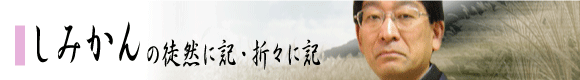 |
 |
 |
|
|
 |
 |
〔06/03/17〕長くて申しわけない、春さん許して… |
【044】 |
 |
|
 |
●12日 春二番 シンプル純粋ねぎラーメン
今日はこの前の春一番よりすごい風。かみさんが自転車に乗っていて交差点近くで風にあおられて転んでケガ。自転車もかごが曲がって、ライトが壊れた。学校のグラウンドの近くの家はきっとすごいよ土ぼこりが。
かみさんがソフト娘とそのスーツを買いに出かけて留守番。蓮太が朝まで起きていたらしく寝太郎。本当は宝生会(三川泉さんの〈西行桜〉他)を拝見に伺いたかったが、税金の申告が迫って(大学の奨学金の申請にいるのだ)、今日中に片をつけたいのであきらめる。一人昼飯、冷蔵庫にラーメンの玉ひとつ有。8日までのだ。よしよし。具も無いので、シンプル純粋ねぎラーメン。(ねぎは昨日どなたかが玄関先においていってくれたので、また土に活けるほどたくさんあり。誰だかまだ不明)。
三川さんの西行、この間青山で二時間ほどワークショップをした明星大学の学生たちが見に行っているはず。その時「きっと西行素晴らしいですよ。」と言っておいた。うー、残念。だからできる事は早くやっておかなくちゃ。
私の〈西行桜〉のイメージは寿夫先生のそれ。
シテが中に座している桜の山の作り物の引廻しが下りる時、黒い柔らかなベールが客席と舞台をつつんだ。内弟子に入ったばかりの私は、楽屋の嵐窓から見ていて息を呑んだ。そして自信に満ちて年功を経た力強い老木の舞。
そしてもう一回はたしか胃がんの手術をなさって復帰後最初の能だった(藤田たがぞう追善能)。前回とはうって変わって実に繊細でやさしい舞だった。「待てしばし、待てしばし・・・。」
明星の学生諸君は十余人。全員足袋をはいてもらって舞台に上がり舞台の構造を舞台の上という視点から説明した後、楽屋で一人の学生に唐織着流し姿の装束を(鬘など全部完全に)付け、鏡の間で面も着け、いきなり幕の前に立たせて「さあ舞台へ歩いて出て行きなさい」(実は夢の中で何にもその曲を知らない、あるいは稽古していないのに幕の前に立たされて「たすけてくれー!」という怖い経験がよくある)。そのあとで全員に「構え」と「運び」、「サシコミ・ヒラキ」などの基本的な型、謡も少し。舞台に座ったままで、質疑応答。この中に西行桜のことなど。大変「しびれたー」。
やってはみたけどやればなかなか進まない、今日は税金完成無理。ああ先送り。
●13日 一寸の虫にも五分の魂 五分もあるのか偉い!五分の維持がなかなか・・・。
朝九時から、青山能の申し合わせ。普通は来週あるはずだが都合により今日しかも普通は九時半からが九時から。気をつけないと誰かが間違って来なかったり遅刻したり。今日は大丈夫だが欠席一人。私は地頭。なかなか・・・。
十一時からニューヨークから来た女優のKさんの初めての稽古。いきなり舞台を橋掛かりからただ歩いてもらって、それから構えと運びを簡単に教えてまた歩いてもらって、そして装束(この前の銕仙会を見てくれたので〈鵺〉の前シテの扮装、黒頭まで)をつけて(棹を持って)歩いてもらって、今度は面もつけてまた歩いてもらって、もう一度面をはずして歩いてもらって、それからまた構えと運び、そして「サシコミ・ヒラキ」を。これで一時間とちょっと。これから全部で十回ちょっとの稽古をする予定。さて明日はどうするか。(通訳してくれる人が明日はいないのだ!)
色々出す手紙の類(出欠の返事や領収書やお弟子さんに序の舞の型付けなど)を書いて帰る。税金の続き。目途は立ったがまだ終わらない。十五日までは無理か。
●14日 おまーく。さあkamaeteうぉーく。さしこみ,ひらき。Sayuu、れふとあんどらいと。
(当日出勤は無いが)11時半から水道橋で永島さんの〈姨捨〉の申し合わせを見学。当日は長山さんの会で見られないし、この前稽古能であった時は沖縄の授業だったので、拝見にうかがう。見所で拝見するつもりで行ったのだが、見所のあかりが全開でついていて一人見てるのが目立ちそうで、幕際から。伺った甲斐有。有難うございました。
三時からKさんの稽古。少し遅れて来る。道に迷ったかな。幕を一緒にあげてみる。そして、ウォーク。さすがに女優さんだけあって、きちんと歩く。「サシコミ・ヒラキ」から「左右」に進む。つい日本語で説明している。「一・二」・・・。また明日。
夜は講座。春の講座の最終回。
私は〈花筐〉(後シテの出から道行きの留めまで。シテ山本順之、ツレ浅見慈一)の地謡。今回のは例会の〈桜川〉から狂女物に焦点を当てたもの。この前〈桜川〉の地謡を謡っていて発見した事あり。「クセ」から〈網之段〉とシテの舞が続いて、最高潮に達した後、最終部分の「ロンギ」で地謡が「いかにやいかに狂人の、言の葉聞けば不思議やな、もしも筑紫の人やらん」と謡いだすが、それは普通解説書などではワキの言葉に訳されている。しかしそれは子方(桜子)の言葉だと思う。ふと狂女の言葉を聞いて、かつて自分が慣れ親しんだ九州の言葉だと、そして自分を探しに来た母であると気がつくのだ。そうなると演出が少し違ってくる。もし今度自分がやるときはそうゆう風にやってみたい。
●15日 八千草さん久しぶり「でるとこでて…」 ウコンの着物が素敵です。
朝十時より〈石橋〉の稽古。
銕之丞師に御足労願って、今度早稲田の大隈講堂での「つつじ能」のときの〈石橋〉の型を教わる。「大獅子」と言う小書(特別な演じ方)で、獅子が白と赤二匹でて通常のものより少し長い「獅子」(普通が六段で、この場合九段になる事が多い)を舞う。白を私、赤を谷本健吾君。いろいろな演じ方がある。今回はごくオーソドックスに。
谷本君は独立記念能で〈石橋〉をやったばっかりだからよいが(成田美奈子さんの「花よりも花のごとく」三巻に石橋を披く話あり。この中では舞い終わって足が攣るということになっている。)、私は実は久しぶり。披きのときに「師資十二段」の小書(これは普通の倍の十二段。息がはあはあ…。)で赤三匹のうちの一匹でやって以来。同じように初演を「披く」と言って大事にされる「猩々乱」は、ずいぶんやらせていただいたのに、〈石橋〉は機会がなかった。ありがたいこと。本当は西村さんとやるべき機会だが、その翌日が〈道成寺〉の申し合わせだからね。谷本さんよろしく。今日から走ろうか。
午後Kさんの稽古。
面を幾つか見てもらう。老人も、鬼も、若い女も、お母さんも、面をつける事によってこの体一つから、その役は生まれてくる。そしてそれを支える「構え」と「運び」、そして「息」。「サシコミ・ヒラキ」「左右」「打ち込みヒラキ」を泣きそうにして何度もやる。OK。「羽衣」の最初のせりふ「のー、その衣はこなたのにて候。何しに召され候ぞ。」をやってみる。よしよし。今度からもっとどんどんいきましょう。
夕方から三菱東京UFJ銀行の稽古。
青山からは地下鉄千代田線で二重橋前へ。明治安田生命のビルから地上に出る。レストラン街を通る。うう、寄り道したい…。明治安田生命の古いビルを中に残した格好のアトリウム、コンサートなどもやるらしい。
銀行の本店、二十二階の和室が稽古場。ビルに入るのに写真付身分証。不可忘。
稽古の曲目はまだ初心の人は私が「では次はこれを。」だが、ベテランの方々(OBの人も来る。)は自分で決めて「今日は○○を御願いします。」 なかなか面白い曲を持ってくる。
今日は〈江野島〉、〈當麻〉、〈昭君〉、〈花月〉、〈海士〉(三人仕事等でお休み、少し前に体調等で一応毎月の稽古は引退と言う人が続いたのでちょっと時間的に余裕が出たがもう少し現役の人は欲しいところ)。
〈江野島〉。これは言葉が面白い。そしてスケール。日本の歴史を考える上でも面白い素材。私としても思い出深い曲。例会で先代銕之丞師のシテの時、私が前ツレで、蓮太郎が初めての子方(五歳)。この子方(二人。この時は鵜沢光さんと)は、後ツレの弁財天(この時は浅井文義さん)と一緒に作り物に入って現れる。作り物は曲の最初に出すので、少なくとも一時間は入っている。引き廻しが下りたその時、真っ赤なほっぺたで大きな目をしっかり開けて、まっすぐきちんと座っている蓮太郎の姿があった。「おお!」と思った。衝撃的なデビュウであったと思う。今写真で見てもすばらしい。
それから子方の時代。今月のお勧めリンクに日本芸術文化振興会のページが入っているが、そこで見るとうちの子供たちで、のべ二十何回か国立能楽堂の子方をやっている。他の会ももちろんたくさんあった。よくしっかりやったもの、この座間から。
稽古などの帰りに子供が言うんだ「父さんまたおこられてたよ」。ばかやろうお前たちのせいじゃないか。銕之丞先生は子供たちには優しいが、私に「お前の稽古の仕方が悪いんだ」。だけどよく前の銕之丞先生に鍛えていただいて、今となってはありがたい、真に有り難い事。
蓮太郎の子方卒業の能〈烏帽子折〉の打ち上げで、野村萬先生が「今度は初シテで〈花月〉などをなさる時にはまたおつき合いさせてください」と仰ってくださったのに、今まで出来なかった。やはり道に生まれていない分、(援護もなく)親も子も疲れてしまって、ちょっと休んでと思った油断。申しわけありません。今度の響の会での〈花月〉は私がやらせていただく。
また別の〈江野島〉のとき、愚かにも悲しい事件有り。一寸の虫にも五分の魂。
〈當麻〉。私の母の出は奈良県御所市(私の出生届もここから。) 私も故郷のように思っている 「葛城」の里。「土蜘蛛」も眠る。金剛葛城の山を北へ巡れば當麻の里。母からその子供の頃、當麻のお寺で「當麻のお曼荼羅さんは…」とよく聞いたと、聞かされたもの。今「死者の書」を岩波ホールでやっている。(大津皇子の声で現銕之丞出演)行かなくちゃ。
三輪の山頂(この山自体が御神体)へは二度登ったことがあるが、當麻の二上山は夕日が沈むところ、大津の皇子が眠るところ、なんだか恐ろしくて登っていない。
〈昭君〉。中国の美女「王昭君」の物語。昭君のお父さんお母さんが、シテ・ツレ。前場にこの二人の凝ったなかなかいい謡あり。
私が銕仙会の能をはじめてみたのがこの〈昭君〉。早稲田にはいって、観世会に入って、すぐに連れていかれた四月の例会。これが歴史的な舞台だった。
従来は前シテが中入りして、全く別人格の後シテ、胡国の夷の大将「呼韓邪単于(こかんやぜんう)」になって出て来るやり方だったのが、この時は前シテはそのまま舞台に残って、別の人が後シテを演じた。能の演出を現在の感覚で見直す大きな一頁となった舞台。これをやったのが観世寿夫。ただひとつの舞台としてよかったという事だけでなく、銕仙会という催しが創造的であったこと、お客とともに作っていた(それが私を能の世界に誘ったのだろう)。
西村さんはこのツレを何回かやっている。二人していつかやりたいが、正直言えばなかなか謡が難しい。
〈花月〉。アメリカからのKさんを紹介したのは「子午線の祀り」などにも出ていた笠原拓郎さん。昔その桐朋の仲間の人たちが先代銕之丞先生に能を習っていて、いつも私たちも一緒にやらせていただいていたその稽古の一曲にこの〈花月〉があった。だから今私が持っているこの曲の型付けもその時のもの。75.4.3とある。あ、内弟子に入ってすぐか。稽古の日も書いてあって7.28まである。四ヶ月やっていたんだ(おかげでこの曲は新たに覚えるという事が無い)。私は一度明野薪能でやっている(その時は残念ながら雨で、隣のホールだった)。
天狗にさらわれて芸能者となっている子と出家した親との、清水寺の境内、満開の桜の下での再会。ヤラセかとも思える、どこか虚無感も漂う曲。役者の人生。
〈海士〉。この秋に青山のお弟子さんが一人この能を舞うべく稽古をしている。(もう一通りは覚えたので、これからだんだん細かくやって行くところ。) 今日のはこの二十一日に三菱の会(「菱水会」‐三菱能楽同好会)があり、そこで素謡のシテをやる、その稽古。ずいぶんいいよ。あとは自信持ってやるのが一番。
よく先代銕之丞先生から、「かな」が扱えてないとおこられたが、今になって人のを聞くと「ああ、その字を延ばしたら意味がきちんと伝わらない。」とかいう事が分かる。
「かな」については先月沖縄での研究室で八重山の歌謡の先生から「能の方でもおっしゃいますか」と聞かれた。ああ、そうなんだ。ただでかい声や気持ちでやっていてもダメなんだ。具体的にどう言葉を活かすか。
そしてなんと言っても、(自信なくとも)自信持って(持っているように)やること!
三人お休みだったので意外に早く終わって、残った人たちと外へでて、「一時間だけビールをどうですか?」と言われて、「はいはい」。東京駅のビアホールにて。一時間が約二時間に。でもこうしてざっくばらんにしゃべることも必要。ごちそうさまでした。
電車のつりポスターで八千草さんに久しぶりに会う。お元気でしたか。素敵です。
駅からの道、満月。昨日は少し冴え冴えとして「月がとっても青いから…」。今日はなんだかボウッとして小さく見える。沈丁花の香り。
● 16日 99円ショップのビニール傘に雨音強し。蝦蟇に降る雨冷たし。
青山の稽古日。一時より九時まで。家をでる時に味噌汁を一杯。稽古の途中でお弟子さんの持ってきた桜餅を二ついただく。声がでない。このところそう。歯の具合もあるか。舌が落ち着かない。何年か前にも声を変えようと思って一年ほど出ない時あり。そのあとよくなったが、また一山だな。越えるぞ。
夕方から雨。久しぶりにジャンジャン降り。相武台前の駅のタクシー全然いないのに客の列。カバンを抱えて歩く。ビニール傘に雨音の強いこと。踏切を渡ったところの歩道の植え込み近くに蝦蟇一匹。おう、もう出てきちゃったのか。あぶないぞ。雨で冷えたのか全く動かない。
夕食はハンバーグ。私の後二人相次いで帰って夕食。強風・嵐、皆早く寝ようね。
● 17日 桜よ咲くな。まだまだ眠っていろよ。
昨夜の嵐がうそのよう。明るく、暖かい。
六時半頃パン屋娘とソフト娘、ワーワーと出かける。ソフト娘は蝦蟇の死骸に遭遇した模様。南無阿弥陀仏。早稲田の所沢のグラウンドまで片道二時間かけて練習に。この間紅白試合でツーアウト満塁でツーベースを打ったそうな(レフトのバンザイのおかげだそうだけれども)。別に行かなくてもよいらしいのだが、さすが厚商で毎日やっていたおかげか、練習を休むと体がうずうずするらしい。
パン屋娘昼過ぎに帰ってきて、腕にやけどの後。釜でやったらしい。三時ごろ、卒業式で着る予定の振袖一式を美容院へ持って行く。一緒にかみさんと駅まで行き(タッちゃんちの木蓮咲きだしている、ああ、あそこの白木蓮も、おお、空き地にスミレだ)、こちらは買い物。パン屋娘はそれから空手娘に。大塚の道場へ。
今日は休日。税金をやり遂げる気が、進まない。買い物は、えぼ鯛、ほたるいか、鶏肉、にんにく、しょうが、しいたけなど。ビールは今日はキリンの発泡酒「円熟」というのを買ってみる。
 帰りに踏み切りを渡って線路際の柵の中に、「つくしだ!」。そんな予感がしたんだ。むずむずしていたんだ。手を伸ばして摘める分だけ摘む。その続きの公園への道にはおいしそうな野蒜が。しかしここはワンちゃん道路だと遠慮する。土筆は例のところ(誰にも教えないぞ)に摘みに行きたいが今日はもう夕方なので、むむむ…。 帰りに踏み切りを渡って線路際の柵の中に、「つくしだ!」。そんな予感がしたんだ。むずむずしていたんだ。手を伸ばして摘める分だけ摘む。その続きの公園への道にはおいしそうな野蒜が。しかしここはワンちゃん道路だと遠慮する。土筆は例のところ(誰にも教えないぞ)に摘みに行きたいが今日はもう夕方なので、むむむ…。
ああ、桜もまだ咲くな、特に明野の桜はまだまだ咲くな。薪能まで待つんだよ。せめて散るのは待つんだよ。明野薪能の会場はバックが背の高い桜の並木なんです。
今まで寒くて、未開の時あり。寒くても満開の時あり。花吹雪の時有り(この時は足袋が桜色に染まった)。もう散ってしまっていたことあり(それでもライトアップによりガクやシベが赤くて結構きれいに見える)。
今までは毎年桜の合う春の曲を選んできたが、今年は初めて〈天鼓〉という秋の曲をやってみる。曲中の温度感を変えてやってみようと思っているから、桜たち咲いていておくれよ。
明日は座間の稽古、それから歯医者さん、それから早稲田OBの青山倶楽部のお稽古、それからこのWEBサイトなど響の会事務局でしっかりやってくれた島田君の送別会、青山ぼこいにて。無事卒業して、大阪へ就職。ありがとう。おつかれさま。元気でがんばってください。明日はゆっくり飲みましょう。
なお彼の仕事は、今後は委員全体で割り振ってやってくれますが、サイト管理の後任にT君。引継ぎ中ですが、よろしくおねがいいたします。
今回の日記は長くなってしまった。たまってしまっていたので一挙放出。
今年になって能を見ていなかったので、もやもやしていたところに早稲田の学生の発表会を見てすっきりしたという人あり。私もこの日記を書くということについては病気になりつつあるか。しかしまたしばらく書けそうに無いが…。こら、よいのだ舞台に励め!
おお、そうだ、土筆の袴を取らなくちゃ。 |
 |
 |
〔06/03/08〕テンテンテントムシお天とさーまの子 啓蟄のナンバ |
【043】 |
 |
|
 |
また駅まで自転車取り。ナンバで歩く。左半身、右半身。左手左足、右足右手。向こうから颯爽と手を振って歩いてきたおばさんがアレ?という顔。
今日は全く春。啓蟄も過ぎてしまったんだと思って、前の駐車場のホトケノザの一叢を見ていたら、中にナナホシテントウ。近所の満開に近くなってきた紅梅に、アブやシジミチョウ。家の梅もちらほら咲いてると思って数えてみたらなんと7,80は咲いてる。結構香る。あらあらモンシロチョウもひらひら。おお、トカゲの赤ちゃんがちょろちょろ。
この間タッちゃんちのマンサクと書いたのは全くのガセネタ。黄色いだけで言ってはいけない!本当はサンシュ(サンシュウ)。家にも咲いてた。但しこれはまだ高さ30センチくらいで花も三輪。かわいい。ガセネタで言っては懲罰委員会にかけられます。反省。
ナンバは最近ナンバ走りの末次選手や古武術の甲野善紀氏の活躍で知られるようになったか。最近読んだ本に『ナンバの身体論 身体が喜ぶ動きを探求する』。桐朋高校のバスケット部の先生たちが著したもの。古くは武智鉄二氏の著作がある。『演劇伝統論』や『舞踊の芸』など(武智さんの仕事は是非検証したいもの)。
私達、能の身体はこのナンバだ。右手が出ると右足で止まる。また「半身」ということも大事だ。これからワークショップなどではこれをテーマにひとつやっていけるかもしれない(また、朝歩いていてダウン症の人たちの歩きに似ている気がした。これも調べてみたい)。
ソフトボール娘は昨日大学の合宿から帰って畳にパタリ。その為ではないが家では皆「パタ」と呼んでいる。高校の行き始めも帰って玄関でよく寝ていた。今日は縁側の日向でグローブの手入れ。背番号は39になったとか(高校時代は24)。応援してやってください。サンキュウ。
昼ごはんに菜の花の胡麻和えと買いたてのおぼろ豆腐。お茶に虎屋の「夜の梅」。
さあ銀行のお稽古に行こうか。
そう「テンテンテントムシお天とさーまの子」はずっと前にどこかで見た戦前のアニメーション(題名は「てんとう虫と蜘蛛」?)の中での歌。時々その歌、旋律が出てくる。記憶は不思議だ。
|
 |
 |
〔06/03/06〕こりゃ春一番か 白梅の蕾は赤ちゃんか |
【042】 |
 |
|
 |
朝ゴミ出し。今日はビン・カン・紙・布。四合瓶にしずくが…。それから駅まで散歩。実は空手娘がパン屋のバイトに(ご飯をしっかり食べていたので)遅刻しそうだと、自転車に乗っていったのを取りに。お蕎麦屋さんのとなりの家、蕾が赤かったのでてっきり紅梅だと思っていたのが実は白梅だった。ははあ、赤ちゃんだったんだね。
空手娘は昨日昇段審査会。三段合格。ちびっ子道場(先生がちびっ子)でもやるか。おめでとう。ところで就職は?卒業式は19日。
昨日こちらは早稲田大学観世会の自主公演。こちらも大成功。よくがんばりました。
少しウジウジしたところがあったのと、男子の謡に少し品に欠ける発声があったが、全体としては【優】をあげよう。
例えば能〈経正〉のシテ(はまちゃん…名前がぴったり『優』)は、最後に装束を着てシテを舞うまでに、仕舞〈舎利〉のシテを舞い、連吟〈巻絹〉(サシからキリまで)、仕舞〈巴〉、〈杜若
クセ〉、〈融〉、〈山姥 クセ〉、〈笠之段〉・舞囃子〈善界〉の地謡を謡っている。しかも手を抜くことなく精一杯。他のメンバーも似たりよったりの大奮闘。パンフレットもよく出来ていたし、お客様も多かった。
『よし!』
賛助出演に(出演順でいけば)法政大学能楽研究会、東京大学観世会、一橋大学観世会、早稲田大学金春会、早稲田大学喜多会、早稲田大学狂言研究会の皆さん。仕舞や狂言小舞を二番ずつ。有難う。
またたまたまな事で、イスラエルから来て日本の映像をとりたいという青年がこの舞台(大学での稽古や楽屋風景を含めて)をビデオで撮影した(学生の英会話の実践教室にもなった)。
他の価値観との交流、社会との交わり、やっぱり大事。
そしてよい舞台を作るには、やはりよく見ること、よく聞く事。
さあ、またがんばっていきましょう。まずは次の新入生をたくさん入れよう。
打ち上げにも賛助の学生諸君やOBもたくさん出てくれて盛り上がる。表参道A4出口の「鳥良」。私は実は歯の具合がよくなく、二次会を失礼して帰る。西村さんが行ってくれる。こういうときに西村さんが頼りになる。
そして今日午前は歯医者さん。この前やった右でなく今度は左がいかれてきた。がんばって直しましょう。そういえばこの前言った眼医者さんはなんと言う名前だっけ。昼ごろから風が強くなった。春一番はもう吹いたっけ。風とともに去りぬ。うーん、浅沼、浅野、荒井、荒木、荒川、村主…うーん。仕方がないので診察券を見る。ああ、そうだ。若年性(モトイ中年性)アルツハイマー発生。
この前頼まれてエッセーを書いた雑誌が送られてきた。『健康』。私の題は「初春や加齢めでたや白鬚や」。1200字との依頼を勝手に1000字と思い込んでいたので、他の人より少なめで、余白が大きく、文章は窮屈。せっかくの機会にしっかり書きなはれや。 |
 |
 |
〔06/03/04〕梅に鶯餅 ありゃマッチャンでべその宙返り |
【041】 |
 |
|
 |
今日はいい天気。おや、家の梅も咲いているではないか。薩摩紅梅。まだ大体が固い蕾で、咲いたのは四・五輪。障子を開けて見ていると、やや、鶯餅が! 鶯色のまん丸目玉の小鳥はメジロ君(本当の鶯の姿が分からない)。いつも柔らかくておいしそうだと思ってしまう。
そうだまたお雛様また出しそびれた。蓮太の幼稚園で作ったのをせめて出しておいてあげよう。
午後から明日の早稲田の自主公演で使う装束(能〈経正〉)を出し(今回はワキも観世会の学生で、角帽子と掛羅をうちのお弟子さんに作ってもらった)、青山へ持って行き、銕仙会から拝借するものとあわせる。さあ、あとはみんながんばってくれるだけ。
昨日はその最終稽古。早稲田の大学内の稽古場で2時から。「先生今日は何時まで大丈夫ですか」と聞くので、「終わるまで」。案の定終わって出たら午後9時。
もちろん地謡も全部自分たちで謡うので、舞手を直すだけでなく、地謡の稽古もしなくてはならないから、一番毎に時間がかかる。だけどこういう時でないと出来ない稽古もあるし、この時だから言える事もある。私も学生の稽古で勉強させてもらっている。
声を壊しかけているのもいる。「明日は少し休めておけよ」。
稽古の前に、義姉が退院するのに新大久保(この駅前に焼き芋のリヤカーを止めたことがある。だけど縄張りがあったら怖いので早々に退去した。)の社会保険中央総合病院へ寄る。手術と放射線治療で三ヶ月あまり。お疲れ様と言うのか、やっぱり「おめでとう」。 でもまだ白血球が2300とか。まあ車で5分のところに住んでいるので通い易い。
高田馬場にのんびりしたバスで出て、(バス停の目の前のビックボックスにて)妻と「草加のフミちゃん」とランチ。9階、新宿方面がよく見える。新大久保へ行く途中の百人町の高層住宅(ここに「東京グローブ座」もある)、その建て替え前の公務員住宅(父は海上保安庁勤務だった。そしてそこから沖縄単身赴任もあった)に学生時代の後半(はじめは荻窪に)住んでいた。
二人と駅で別れて早稲田へ歩く。考えてみればもう35年通ってるんだ。殊に百人町に住んでいた頃は毎日この道をテクテクだった。今度は末娘もこの道を通う。
「まだ自分も若いつもりだけれど 山本順之先生から引き継いで学生を教え始めてもう25年を過ぎてしまったんだなあ(どこかの雑誌にあったが、「女は35歳から」だとしたら、「男は53歳から」、美しくね。)」などと思いながら歩く。
もちろん新しい店が出来たりはしているが基本的には変わっていない。早稲田松竹では「太陽がいっぱい」本日まで。古本屋に今度の学生の自主公演のチラシが貼ってある。『よし!』。 アヴァコスタジオのところを通らせてもらって学生会館へ近道。予定の時間より少し早く着いたので一階のロビーのベンチで30分昼寝。
今の学生会館は三代目。私の頃は第一学生会館。隣に第二学生会館もあったがロックアウトされていて、窓ガラスは全部割れた無惨な状態だった。やがて改修され、小さいながら能舞台があり(学生が立て籠もった時には査問室になっていたといううわさがあった)、そこを稽古に使っていたが近年現在の学生会館が出来て移った。元のは二棟一緒に全く建て替えられて小野記念講堂(柿落しに装束付舞囃子〈高砂〉を舞わせていただいた)の入った校舎になっている。
9時に終わって(ちょっと本屋によって)帰れば11時。今夜は肉じゃが。蓮太が12時ごろ帰って、晩飯。あとの体育会二人は合宿でいない。大阪娘はまだ帰ってこない。静。カサが少ない。やがて二人になるさ。お、温泉行けるかな。
卒業予定者に「不可」有。しかも就職も決まっている! 追試追試。がんばれ。
『ありゃマッチャンでべその宙返り』 |
 |
 |
〔06/03/02〕蛍の光 まなこの涙 |
【040】 |
 |
|
 |
今日は末娘(ソフトボール娘)沙羅の卒業式(神奈川県立厚木商業高校)。午前十時より。幸い今日は仕事が無く、夫婦で出席。雨やんでよかったね。しかも体育館は寒いかと思ったが意外に大丈夫。
開会に起立して、フト自分の高校のときの卒業式を思い出す。あれは渋谷公会堂だった、そして君が代斉唱に起立せずに歌わなかったんだと思い出したところで、『君が代』と来た。坐るわけにはいかないが、歌えるものでもない。
私の高校、都立富士高校では私の在校中に生徒会の決議によって制服着用義務が廃止された(その時の制服委員会の委員長が親友のH君、彼のことをこのところしきりに思う、いつか書こう)。 だから卒業式は初めてのスーツ(ただし誰かからのお下がり)で行ったと思う。
今日は皆制服。ブレザー。ネクタイはゆるゆる、腰パン、超ミニ(但しソフトボール部やバレー部?はスカート長い)。「こら!きっちりせい。」
しかしその彼ら彼女たちが泣くのだ。もう名前を呼ばれて一人ずつ起立するときに泣いているのもいれば、最後の別れの歌(「蛍の光」ではなく…)を歌うときにはもうずいぶんが、そして担任の先生に何か一言言ってその先生を先頭に退場するときには半分以上が涙なのだ。よしよし(お目目の化粧が流れるぞと心配な子もいる)。おかげでこっちもハンカチを使う。
各教室に分かれて卒業証書はじめいろいろ配布物。検定等の表彰状。しかし、「こら!うるさいぞ。勝手に動くな。はしゃぎすぎ。いつも授業中どうだったんだ?」 殊にソフト部。このクラスに5人固まっている。(いつも授業中は睡眠のため大変静かだったらしい。) まあ明るくてよかったか。
国際経済科は一クラスで担任の先生も三年間持ち上がり。39名預かって二人今日一緒に卒業できなかった生徒がいることを自分の反省を含めて話される。ここでも涙。ジュースで乾杯。三年間有難うございました(沙羅はうちの家族で初めてのオール5)。
解散の後ソフト部はやっぱりグラウンドへ。監督、後輩たちとの挨拶。よく三年間がんばってやりました。春夏全国制覇という結果。しかも県立で、甲子園だったら新聞一面に載るところ。あの怖かった監督がさすがに今日はニコニコして、一人一人に花束を贈っている。有難うございました。写真をとったり胴上げをしたり、なかなか後輩たちとの名残が尽きない。(待っている親たち、寒さと空腹。)
ようやく切り上げて(すると後輩たちはすぐにランニングを始める)、今度は地元の商店会への挨拶廻り。いつも応援してくれた方々。ここでも生徒たち一人一人に花束をもらったり、八百屋さんでは焼き芋。有難うございました。
焼き芋のあまりにいい匂いにバス停で早速いただく(そうだ学生時代焼き芋屋のバイトでリヤカーを引いた事があった)。本厚木の駅ビルでお別れの昼食会。この時点でもう2時半。生徒父兄あわせて16名。三年間朝から晩まで毎日一緒にがんばった仲間(交通不便なところからは毎日送り迎えしたお父さんもいる)。ここでも話は尽きない。ようやく六時ごろ解散。もう明日からは敵味方。実業団へ行く人は明日から寮生活。うちのも早速に明日から大学のクラブの合宿へ。またグラウンドでみんなとも会うだろう。怪我の無いようにがんばろう。元気で。
今日は税金の申告の準備をするはずだったがちょっと無理。タッちゃんちのマンサクの花が黄色く伸びてきたね。その隣の沈丁花の蕾も膨らんできたね。そう奨学金の申請のためには早く申告しなくっちゃ。明日はこちらも早稲田の稽古。日曜日に発表会、明日の稽古は厳しいよ。
多田先生からNHKの放送文化賞受賞のお知らせをいただく。
泥中で栗を拾ったようなうれしいご気分とのこと、おめでとうございます。
http://www.nhk.or.jp/bunken/bunkasho/index.html |
 |
|
 |
|