|
|
 |
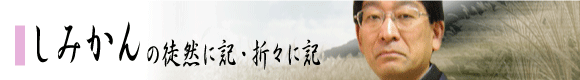 |
 |
 |
|
|
 |
 |
〔06/04/17〕歯科待合室で今日はいい天気だねとおばあさんに三回 |
【049】 |
 |
|
 |
 今日はいい天気。少し暖かくなりそう。玄関のすぐにカタバミたち。またミツバが伸びてる、朝ごはんに。アケビの蔓がぐんぐん。サカキの花が黒い玉ころになりかけ。若芽を花のように出している伽羅の垣根の間から、ミヤコワスレ・チュウリップの蕾がふくらみ(今日咲きそう)、ミント、柿若葉、出初めは玉蘭と間違えられた鳴子蘭・白のフリージア・シャガ・ヤマブキの花。 今日はいい天気。少し暖かくなりそう。玄関のすぐにカタバミたち。またミツバが伸びてる、朝ごはんに。アケビの蔓がぐんぐん。サカキの花が黒い玉ころになりかけ。若芽を花のように出している伽羅の垣根の間から、ミヤコワスレ・チュウリップの蕾がふくらみ(今日咲きそう)、ミント、柿若葉、出初めは玉蘭と間違えられた鳴子蘭・白のフリージア・シャガ・ヤマブキの花。
「かくて大原に御幸なって、寂光院の有様を見渡せば、露結ぶ庭の夏草茂りあいて、青柳糸を乱しつつ、池の浮き草波に揺られて、錦を晒すかと疑わる、岸の山吹咲き乱れ…」 ≪池の…いや違う、それはさっき言ったぞ…うーん、そうだ≫ 「八重立つ雲の絶間より、山ホトトギスの一声も、君の御幸を待ち顔なり。」 ≪ホッー。≫
一昨日横浜能楽堂で松音会(泉泰孝・雅一郎両師の会)有り。やりなれないことに素謡〈大原御幸〉のワキを仰せつかる。いつも能の時は宝生閑先生の名調子を聞くところ(ことにツレの内侍の役の時は作り物の内に一人残された孤独感と足の痺れの恐れの中で聞いている)。ここのところ観世流は聞きなれた下掛宝生流と節がずいぶん違う。少したっぷり目に謡わせてもらう。しかしヤマブキの後で、一瞬、あれ、なんだっけ。ああ、なかなか心臓に悪い、とてもありがたいお役。
その他に何番か舞囃子のお地(地謡)。あるおシテの方が、「この間座間の方で能のお話をなさったそうですね。今日も来ていますが私の妹が伺いまして、とても良いお話で…」 恐縮です。有難うございます。世間は狭い。座間の茶道連盟の総会でのお話。
もちろん私に「茶と能」というような正面きっての講義は出来ないから、いつか小田原の先生に呼んでいただいて、熱海のMOA美術館でのお茶会に、半能〈西王母〉を舞わせていただいたときの体験―その打合せに伺ってお茶室でいただいたお酒とお茶のおいしかったこと―から始めて、能の面白さをお話した。
もともと「能の楽しみ方」という題名がついていて、お話の前日までは簡単に、能を見るときの色々な見方・角度というようなことでお話ししようと思っていたのだけれど、当日になって、フト、あれ、やっぱり能を演じる楽しみも言わなくっちゃと思い、そして間際になってみれば、(秀吉が能をやっていたことをお話しようと思ったことから)あれ、能の歴史や文学などを調べる事も楽しみのひとつになるぞと思い、結局、能を(1)見る(2)演じる(3)調べるの三つの方向にそれぞれまた色々な楽しみ方があるというお話になった。(ああ、もっと前からきちんとまとめておかなくては。ここでも心臓に負担)。
質問に「能と狂言の関係は?」といういい質問が出て、言い忘れそうだった狂言の中にあるお茶をあつかった曲を幾つかお話しすることが出来た。〈附子〉の中に出てくる大天目やお掛け物のことや〈茶壷〉など。
話のあと、控え室でいただいたお菓子、お抹茶のおいしさ。心臓のお薬。
(えーと今日に戻って)10時に歯医者さん。
〈小督〉を一曲謡ってからと思っていたら少々遅刻。六月の銕仙会定期公演にて小生のシテ。ずーっと以前に若松さんのおシテであり。その時はツレの小督の局が永島さん、私がトモの侍女(今度はツレが西村さんでトモが浅見慈一君、今週彼は〈蝉丸〉有り。地を謡いに行く)。このところ銕仙会の例会ではあまり出ていない(本来は秋にやって好い曲)。その型付を若松さんが貸してくださった。謡本に銕仙会の大先輩、故山口幸徳さんがお書きになったもの。
山口さんは三菱銀行謡曲部を60年ご指導になり、「引退しますから(能のシテは私が入門する前に引退なさっていた。)あなた行ってくれませんか」と、私がお稽古に行くようになったその人。今度の道成寺の鐘後見でも着る予定の長裃を形見にいただいている(上等で折切れしているのでまた修理しておかなくては)。
山口さんは(はじめ山口先生と呼ぶと「私はあなたの先生ではないから山口さんと呼んでください」とおっしゃった)、若い頃絵描きになりたかったとのことで、また大変な達筆でもいらした。山口さんの会「荷風会」の当日には、いつも楽屋に筆で書かれた巻紙の番組が貼られていて、とても素敵だったので、実は一枚頂戴して今も手許にある。 お手紙を頂戴するとあまりの達筆になかなか判読に困る事もあった。その型付。これはなかなか一見では読めない。しかしよく見ているとだんだん…。よく読み込もう。
(えーと歯医者に戻って)待合室にかなり高齢の御夫婦。小さいおばあちゃんが私に話しかける。「今日はいい天気でよかったね。あなたこの辺?私は谷戸…」 三回ばかり。おばあちゃんもう前歯あんまりないよ。腰というか背中、ずいぶん曲がってるが、「歯ぐらいはね、病気になる人もいるし、人生色々だけどね、ここまで生きて来られたらもうそれでね…」 おじいさんに「お前先に見てもらえ」と言われると、「わたしゃいいよ」。これが二回。先生が「ま、ま、どうぞ、どうぞ、見ましょう、見ましょう」。
私は抜糸。エイエイエイと、あっと言う間。「ではまた来週」。 思わず胸に手を置くと、「あ、いやまだやりませんよ」。 奥歯の事。今のところが落ち着かなくては、なかなか噛むのに苦労してるからね。
ドウダンの花盛り。八重桜の桜餅の連想してしまう。私は道明寺が好き。午睡。
夕方のジュウニヒトエの青い蛍光の幻想。東の一叢にはスギナたち。西の一叢にはスズランの並木。猫の額もなかなかたいしたもの。ネギを活ければミミズがうじゃうじゃ。ドクダミも出てるが、お、紫蘇が出始めたか。まもなく初鰹。
●4.16 青い蛍光の十二単の森出現 中にスギナの大木有り
今日はオフ。以前住んでいた4丁目(今ここは5丁目)のKさんからお昼に天ぷらを食べに行こうとお誘いの電話あり。御主人は鹿児島の県人会に東京へお出かけ(奥様は宮崎都城の御出身)。 かみさんと二人のこのこ出かける。町田の小田急の上の新宿・つな八。ようやく仕事が無くても稽古が無くても普通になってきたが、前は「あれ今日は何もなくてよかったのか」とよく思ったもの。出掛けるのに手ぶらの時は何か持ってなくて良いのかと思ったもの。なんだか今日は気楽に出かけられる。ようやく肩の力が抜けてきたか(しかしやっぱり仕事や稽古が無くっちゃね…)。
昼からビール少々(まだ抜糸前だから)にお刺身つきの天ぷらを頂き、またケーキにコーヒーまで頂き、なんという平和な。
舞台で必要な時だけコンタクトをしているが、それがなくなってきたので、メガネのイワキによる。ここも以前にKさんに紹介していただいた。応対が丁寧で安心感がある(コンタクトの眼科の先生が美人)。乱視の入ったone
dayのコンタクトを試してみる。
今までのは近視だけだったのでまあどうにか見えるという程度だったがこれは良い。しかし、近くの新聞はダメ。これは○眼。ハハハハハ、遠 - 近 - 乱!
コンタクトは、シテでも面をかけない直面のようにまばたきが出来ない時はしない。地謡でも静かな曲の前列では、うまく瞬きのタイミングがとれず気になってしまう事があるのでしないことにしている。おもに後見などの時。
夕方帰る。踏み切りの前に家に藤と八重桜が咲いている。しかしまた寒くなってきた。庭のジュウニヒトエが青い蛍光の森。まだ満腹感、つい夕寝。起きて食器を片付けながら〈花月〉を謡う。
「げにげに鶯が花を散らし候よ。それがし射て落とし候わん」。 歯ぐきが、「いて!」。
それからフト〈井筒〉を謡う。「暁毎の閼伽の水…」。この前沖縄の授業に行った時、〈井筒〉の舞台で全然憶えていない夢を見て、一人でフト謡った。午前中は授業がなかったので毎日この〈井筒〉を一曲謡っていた。最後の日は立って一曲舞ってみた。これまた「初心」となるなり。
響の会のパンフレットの校正の作業進む。皆さん有難う。 |
 |
 |
〔06/04/13〕花の芥を踏んで帰れば 多田先生の怒り |
【048】 |
 |
|
 |
今日は朝銕仙会の申し合わせ、そして午後は青山での稽古日(1〜9時)。帰ってご飯を食べて(アジ君)、新聞を呼んで、明日になって、メールを開いたら、多田先生よりの怒りのメール。この前お宅に伺った折におっしゃっていたリハビリの制度の問題。
私のおじもこの前お風呂で転んで首の骨を折って全身不随となり今懸命のリハビリ中。4月8日の朝日新聞の朝刊に載った先生の寄稿は拝見していたが、私もこれを皆さんに広めてみたい。
各位殿
4月8日に朝日新聞に載った、新たな診療報酬の改定にたいする、私の投書をお目に かけます。私の怒りがお分かりになると思います。受け皿もなしに、突然の通告です。患者はみな困っています。
僕はNHKを動かして、取材をしてもらうほかに、新聞などメディアにも呼びかけています。あなたの周りで助けてくれるところがあれば、呼びかけてください。政治家にも実情を訴えてください。人間をだめにする改定です。僕は怒っています。どうかよろしく。
多田富雄
そう今朝ツバメを確認。花びらが飛んできて、フト 空を見上げたら、すーい、スーイ。
日記としては三日坊主をまぬかれたか…。
●4.12 色のりきゅうは利休とも利久とも 三日坊主
歯はハハハ、まあまあ。少しづつ声を出してみる。まだ口は全開に出来ないがまあ。昼前に郵便局へ。振込みと書留と手紙と葉書。
お礼やお返事につい日を置いたり、支払いが遅くなったり(実際お金がない時もありますのでちょっと待って下さいね)。ごめんなさい。
振替三枚。
足袋の伊勢屋さんへ。誂えの足袋六足分。一足4,400円。
私はずっと毎日この伊勢屋さんの足袋。普段はただ25センチと言って買ったものだが、舞う時の足袋は誂えのもの(コハゼに「シミズ」と有り)をはく。ぴたりとしているのでさすがに長く座る時は25cm。それでもやっぱりはく時には(だんだん縮んで来るし)、引っ張ってはかないとはけない。甲の縫い目がすわりだこに当たって痛い。しかし普段にこそきちんとしたのをはかなくちゃ。足というものはなかなか自分の意思だけではきれいになっていかないから、能役者はいつもいい足袋をはいてないといけない。正直言ってこのところの足袋の出来はあんまりよくない。質を保つ事は大変なことだろうと思うががんばって欲しい。もし良い足袋が出来なければよい能はもう出来ないと言ってもよいと思う。足袋は装束のひとつ(そういうことも能楽学会は取り上げて良いよね)。伊勢屋さんありがとう。
檜書店さんへ。月刊観世一年分とこの間送ってもらった横道萬里雄先生の『体現芸術として見た寺事の構造』(岩波書店)分。
本当にもっと能の世界がわっと広がらないかしらン。檜さんがんばってますよね。横道先生には響の会の集いでお話していただいた事あり。もう90歳を迎えられる。
能〈當願暮頭〉の時(1991国立能楽堂にて復曲初演)には、ワキと地謡で声明の部分あり、その声明を教わった。この間の〈鷹姫〉では岩の役の「あたさらさまら…」という呪文のようなところで印を結ぶことを教わった。先生はいとも簡単になさる。我々はエーどうなってンの…? だがやってみるとなかなか面白いのだ。
この御本の中にもそれぞれあり。「体現芸術として見た」と本の名にも有り、詳しく「どのように」と記載あり。昨日紹介した国立の声明公演の記事もあり。先生には私達の能までよくご覧頂き、まことにありがたい。背筋が伸びる思い。
なお付録の(と言っても114ページも有る)「宗派別寺院行事一覧」共編者の一人は小早川修氏夫人の小野里法子さん。
夕方からこの前延ばしてもらった座間の稽古。ちょっと小さい声で今日は我慢してください。明日は銕仙会4月例会の申し合わせ(私は〈七騎落〉の地謡)と青山稽古日。本番までには何とか。それにしても〈七騎落〉はあんまり謡った事ないなあ。
昨日の日記の「城ヶ島の雨」のところを見ると、「利久鼠」と有り。私は利休鼠と書いた。辞書を見ると両様有り。ああ、少し雲が晴れてきた。これで三日続けて書いてるがハハ三日坊主、みっかぼうずー。ホーホケキョ。 |
 |
 |
〔06/04/12〕雨は降る降る ガセネタ摘発第三号 雲林院でなし草紙洗 |
【047】 |
 |
|
 |
今日は稽古能〈小塩〉と〈定家〉をお休み。歯医者さんへ。しかしあっけなく「大丈夫でしたか。あ、経過いいですね。では、来週抜糸しましょう」。稽古能見学だけでも行けばよかったか。でもやっぱりどっか体が緊張して、疲れてるんだよね。腫れは前回よりは少ないか。雨の休日を有難う。
歯医者から帰ったら妻が泣いている。ラジオで米良美一さんの「よいとまけの歌」。もう「もののけ姫」から10年経つんだね。米良さんも35歳とか。うちの洗面所にはまだ“コダマ”がいて、暗いとぼーっと光ってるよ。
NHKで流れた米良さんの「城ヶ島の雨」の歌を宮崎監督が聞いて…とか。
♪ 雨は降る降る 谷戸山の森に 利休鼠の雨が降る…
障子をあけて雨の谷戸山。けむる。バットしかし、家の前の駐車場の向こうの畑の向こうの資材置き場が建売住宅になってしまって、その向こうの谷戸山公園の景色があまり見えなくなってしまった。新緑がもやもや、右手の家の立ってないほうはまだ桜が見える。うちの庭では紅葉の葉の赤ちゃん。これも実生を鉢で育てていたものを土に移した。榊と梅の間。あまり大きくならないように時々剪定。全く自己流。
昼は二人で全粒粉入り手延べそうめん「島原小町」。ゆでたままでいただく。昨日となりから頂いたかき揚げが一枚残っていて、だしもとらず、ただしょうゆをゆで汁で薄め、かき揚げを半分こしてネギとショウガ。これはうまい。
昨日書いたものを見ていて幾つか×を発見。ガセネタはすぐ正直に告白するべし。奥川氏の九皐会での能は〈雲林院〉ではなく〈草紙洗小町〉なり。失礼つかまつった。あいや、許されい(書かなくてもいいか…、ガセネタの元は西村氏が誤解)。
〈雲林院〉は長沼範夫氏。他の×は密かに訂正を…。
昨日二冊の御本を頂戴した。
山下道代著『陽成院―乱行の帝―』新典社刊と『春秋』2006年2.3月号春秋社発行
山下氏は鹿児島の御出身。『王朝歌人 伊勢』 『歌語りの時代―大和物語の人々―』など御著書あり。能も稽古されている。
陽成院の母は藤原の高子、その兄は基経。と来ると世阿弥自筆本〈雲林院〉の世界。天皇の后である高子をさらわれて兄基経が鬼となって追いかける話。現行の〈雲林院〉はそれをうまくソフトにした全く異なった作品。それでもその物語が下敷きになっていると読み込むととても面白い。古式のものは先代銕之亟師が復曲して以後色々な演出で上演されている。今度五月に大阪の大槻清韻会で浅井さんが上演の予定。さてどんな風になさるか。
陽成院の和歌は後撰集巻十一にただ一首との事。
「つくばねの峰より落つるみなの川恋ぞつもりて淵となりける」
(百人一首では「淵となりぬる」)
『春秋』は田村博巳氏よりいただく。
田村氏はこのところ大阪の文楽劇場にいらしたが今度国立能楽堂に赴任された由。氏の文章は『鳥養潮の創作声明の世界―「現代の日本音楽」シリーズによせて』。
以前三宅坂の国立劇場にいらして、私が1992年に間宮芳生さんの『白い風ニルチッイ・リガイが通る道―最初の男と女はとうもろこしの実から生まれた』に出演した時(山本順之氏他と)の演出をされた時からの御縁。この作品はネイティブ・アメリカンの口頭伝承や儀礼歌を能の謡とパーカッションを使って蘇らせた作品(この楽譜とCDは春秋社の「現代の日本音楽」の第二巻として刊行されている)。 なかなか面白い経験だった。
田村氏は声明と現代音楽の分野でも重要な役割を果たされている。
近くは山本東次郎氏一門が参加なさった宮沢賢治原作『論議ビヂテリアン大祭』(吉川和夫作品田村氏演出)の何度目かの再演でお目にかかっている。
『白い風…』も再演しましょう。
氏以外の記事では小川典子さんの『ピアニストの「練習」人生』。
いつも私達が受ける質問「一日、何時間くらい練習するのですか?」。同じ事。練習(稽古)しなけりゃ出来ないし、もちろんたくさんやったほうがいいだろうがやったからできるものでもないしやったからあんしんはできないしやらなきゃふあんだし…なかなかじっさいじかんはとれないし。私達は体全体での表現だから、練習時間だけが稽古だと思っているとまったくあるところから進まない。どうやったら自分の言語を持てるか、そのための稽古が必要だ。
このパソコンは蓮太郎の部屋にあり、窓から見える大山・丹沢はけぶって今日はまったく見えない。寒い。もう暗くなってきた。灯油は三月でちょうど使い切って買ってないから焚けないし…。
そうだツバメはどうしたろう。いつか駅で見たのに。相武台前の上りホームで電車を舞っていた時フト駅前のロータリーの上を見上げたら、なんか飛んでいる。ああ、ツバメだ。もう来たんだ。おお、いっぱいいるじゃないか。相武台前の駅はホームは一階駅舎は二階、それにつながって小田急のスーパーとその上に「小田急相武台アパート」あり。そこに巣を作るのか大きく旋回している。でもここんとこ見ないな。寒いからまた南へ退避したかな。
蓮太郎からTELあり。「内定もらった」。おめでとう!やったね。でもしかしバット、残念、今日はまだ飲めないよ。 |
 |
 |
〔06/04/10〕海棠こぼれる歯科 ううう…と呻くしか |
【046】 |
 |
|
 |
●4月7日:花冷えの直弼戒名二十一字あり
曇り、時々薄日有り。朝玄関脇の蕗の収穫。130本余り。早速ゆでて皮むき。
午後かみさんと出かける。小田急線経堂駅に降りて歩く。経堂のお寺から東京農大(付属高校の入学式らしい)から世田谷八幡宮、豪徳寺を経て小田急線豪徳寺駅に至り帰る。都内復帰の第一候補地。
豪徳寺は井伊家の菩提寺。「井伊さん」は代々能を好まれたそうな。鵜沢雅さんがよく「井伊さんが…」とおっしゃっていた。近年も彦根のお城での演能有り。先代銕之丞師の〈安宅〉(子方は蓮太郎)など二三度うかがった。
映画〈梟の城〉のロケも彦根のお城の横にセットを組んで有り。これは秀吉が能〈吉野詣〉(秀吉が作らせたいわゆる太閤能の一つ)を舞っている最中にものすごい雨が降ってくるシーン。装束付けに行って、私も後見に座っている(最近の映画では〈博士の愛した数式〉の中で薪能のシーン有り。現銕之丞師の〈江口〉。私は地謡。浜離宮でのロケ。見ていないのだが地謡はほとんど映ってないらしい。映画の撮影は時間がかかって大変だが、私はとても面白いと思っている)。
広くて落ち着いた境内。いろいろ整備中か。招き猫のお堂有り。奥の墓所にお殿様方の墓あり。一番奥に井伊直弼大老の墓あり。この戒名は覚えられないよ。
建立中の三重塔(本体は白木も美しく出来上がっている。招き猫の彫り物有り)の落慶法要が五月に。能〈善知鳥〉に「造立供養にあずからん」とあり、私もまた来てその報恩を頂戴したいもの。美しい紅枝垂れ有り。「咲きも残らず散りもはじめず。」
世田谷線に沿って豪徳寺駅へ。洋服屋と花屋さん多し。かみさんの服と山椒の苗(300円)買う。200円のラーメン屋有り約一名の「?」表明により、そこをあきらめ駅のサンマルクカフェにてデニッシュとコーヒー。相武台前の花屋でも黄色いポピーを二株120円で買う。
帰宅して、締め切りを過ぎていた響の会の当日パンフレット用の文章を書いて送る(遅くなってすみません)。
蕗味噌、うまい。軸の方は鳥とこんにゃく、あぶらげ、にんじんなどと煮物。うまい、お代わり。今日のビールは、もとい発泡酒は、キリンの500ml×6で889円。
●4月6日:花月 「月は常住にして」とは言えど無い時もあるよ 春は花
朝、谷戸山方面へ散歩。四方に鶯の声。帰りにタラノメを摘む。さっそく朝からてんぷら。うまい。この香り!
明野の装束を出して青山へ持って行く。午後青山の稽古。この前国立で〈摂待〉の稽古ありそれで延ばした分(そのおかげで玉突き。今日の座間の稽古の予定を12日に延ばしてもらう)。夜7時過ぎ青山より、西村君と新宿の荻原女史宅訪問。懐かしいポーランドよりの客人二人。榮夫先生も後からみえる。荻原さんの手料理にワイン。去年六月に五日間ワルシャワで演劇の学生さんたちに能のワークショップ有り。榮夫、銕之丞、西村、小生、そして荻原さんのメンバーにて、能〈羽衣〉の部分と〈野守〉の仕舞。お互い言葉が分からないから大変だったが、また是非やりましょう。
駅からの帰り道、桜の下を通ればこずえの間に半月有り。是まさに〈花月〉なり。
帰ってみると、アケビの芽のてんぷら有り。これまた珍味なり。
●4月5日:乱拍子の顔 輝きしまる いつも童顔でニコニコの飯田氏の顔
朝10時より宝生にて〈道成寺〉下申し合わせ。今日は能楽堂の都合により鐘なし。しかし我々鐘後見も所定の位置に座る。小鼓は九州より飯田清一氏(昨年は〈長崎の聖母〉でお世話になった。後見に幸先生)。乱拍子、他流と違って幸流は掛け声が短い。シーンとした間、これをシテと鼓がお互い息で計る。私も初演は幸流。大倉流もかつては短かったそうな。
あとはもう一度26日に申し合わせ有り(その時は〈花月〉も)。乱拍子は直前の本申し合わせでは省略すること多し。宝生流でも23日に道成寺が出るため、鐘は24.25日で作る予定。
昼を榮夫師と銕之丞師と四人で「かつ吉」にて。地頭の榮夫先生まもなく80歳。実は先日二月に手術有り。今日はひれかつ。お元気なり。
その後二人で秋の響の会研究公演の番組の詳細を相談する。これより出演交渉へ(ここまで書いて長い中断。時間があれこれだがとりあえずまた今日から始めよう)。
●4月10日:ガセネタの摘発第二号 伽羅の茶色の玉は「蕾」ではなく新芽なり
ファックスにて響の会当日パンフレットの一校来る。今秋の研究公演の予定この間決定したのでまもなく発表できる予定。
朝この間の山椒の苗を植える。美しく十二単が咲きだしている、その横、榊と実生のみかん?きんかん?(まだ40cmほど)の間。山椒は二度枯らしている。原因不明。今度はどうか。猫の額(猫が自分の額はそんなに狭くないというか)の畑に二葉が出ているのはかぼちゃ。その横にジャガイモの芽も出てるね。冬の間生ゴミを鋤きこんでいたから。ここは今年はオクラを植える予定。玄関の前に三つ葉がけっこう出て、摘んでお昼の味噌汁に。正月の松飾りを枯らしておいたのを燃やす。もう四月だよ。さすがによく乾いてよく燃える。こんな小さな焚き火だけれどもそしてあっという間だけれどあったかい。それにしても寒いね。三月初めの気温。
垣根の伽羅の新芽が伸びだして、まるで花のよう。いつか花の蕾のように書いたが、それは間違い。その垣根の間からのぞいている山吹の蕾とまぎれるように「咲いている」新芽。実生の柿の若葉もかわいい。鉢のけやきの赤ちゃん葉っぱも広がり始めてかわいい。
早めに昼ご飯を食べて歯医者さんへ。二回目の手術。左の下の奥歯だと思って行ったら、「こっちからやりましょう。こんなに進んでるとは…」と言って左下の前歯。アーンと口をあいているだけで、最初の麻酔が痛いがすぐに感じなくなって、どんな風にやられているのかよくわからない。が、先生「丸鑿」?! 看護婦さん「少し衝撃がありますけど…」。え、僕に言ってるの? 先生「はい」。 看護婦さん「はい(ガツン)」。 「はい」。ガツン。……。 庭の海棠の花がこぼれている…。
明日また来ます。おかげでぐっすり昼寝。そしてこれを書いてる(7.6.5日の分にも少し書き足して)。
空手娘もずっと寝ている。朝6時半にパン屋のバイトに行って1時頃帰り昼ごはん食べて新聞読んでから。昨日港区の空手の大会。一般女子で組み手と形、両方三位。ソフト娘が応援に行ったらしい。大阪のマンドリン娘も演奏会だったらしい。大阪学生マンドリン連盟。うまくいっただろうか。
口が開かないので晩御飯はうどんを飲み込む。湯豆腐。おからの煮物うまいのが出来てるのに、ああお酒においしそう。今年歯の治療を始めて確実にお酒の量が減ってる。おかげでお腹の出具合も減ってる。
明日はやはり稽古能と赤羽のお稽古お休みします、すみませんよろしくお願いいたします。
●4月9日:京冬青庵舞台に白き花あり名を問えば 「あれなむ利休梅」
京都へ日帰り。青木道喜さんの会。6時半に家をでて、新幹線新横浜からのぞみ(ほぼ満員)、京都駅から地下鉄で烏丸御池。荷物軽くと紋付袴に羽織で行く。そのせいか京都駅で「御所はどう行きますか」と聞かれるが「ワシャ知らんがな」。その人の持っていた地図を見て「ああ、この地下鉄で丸太町で降りてください」。地下鉄もずいぶん込んでる。地図を持った人大勢。京都は東京より桜が遅いし色々な桜があってこれからというところも。京都の人はこういう日は人が一杯なので行かないらしい。いつかゆっくり京の花見もしてみたい。
今日の会は小会とて玄人は青木さん含めて六人。素謡もあんまり省略ないので謡いデあるが、青木さん手抜きなし。幸い遠い曲もなく、庭を見ながらにウンコラ謡う一日は楽しい。合間には、お茶室でお抹茶もいただく。お菓子、結構でした。お昼のお弁当もなかなか。おかずの数、質。これはお酒無しにあっという間に食べるのはまことにもったいない。今度うちの会もここでやらせていただこう。来年花見を兼ねてはどうだろう。
帰りは18時発小田原停車のひかりで、小田原から小田急。新幹線よく寝ました。帰って晩御飯。鹿児島のたけのこの炊き込みご飯。
●4月8日:はれちゃってはなまんかいでおくないでまんいんでほんまかい
明野薪能。
今日は午後必ず雨が降るとの予報。屋内(イルブリランテホール)でやることに決定してもう中に仕込んでいるとのこと。銕仙会に町のバスが来てそれぞれ車で行く人以外はこれに乗って行く。少し早く行って装束を揃え(銕仙会より拝借のもの有り)、バスの中で配られるお弁当を先にいただく。皆(西村氏―銕仙会の皆は国立で催し有り、研能会の人たちと矢来の奥川君―明日は九皐会で〈雲林院〉のおシテがあるのに有難う、笛の松田さん等)集まる頃、すごい雨。やっぱり来たか。13時発。
しかし隅田川辺から寝てドライブインで休憩に起きてみたら、あれれ、いい天気でポカポカ。中でやるから揚幕はいらないと置いてきたけどやっぱり持ってくるべきだったかな。どうしようか、でも急に外に舞台敷けないだろうしなどと色々考えながら到着。やっぱり晴れてる! さくらは満開! しかしホール!
実は装束や型を考える時、あの暗い野外でどうかと考えていたので、ホールの中は暖かくていいけれど、そして明るくて、舞台の上の敷き舞台だから落ちる事もなくて安心だけれど、ちょっとイメージを作り変えなくてはならない。
〈天鼓〉は秋の能だけれど今日は後シテの着付けに撫子に蝶の唐織を使う。前シテ「またこの秋に」というべきところを「この春…」と言い間違え…。
字は「明野」だけれど、ここの舞台で面をかけて舞うのは、いつも暗くて怖くて、音がよく聞こえなくて孤独で、寒くて足は冷たいし滑らないし大変だけれど、舞台の後ろの桜たち、そして町の人たちの自分たちでこの催しを全部やっているその力が助けてくれ、そしてその笑顔が楽しみ。もう13年。
このところ地元の子供たちの狂言(万蔵氏のところの若い人が教えている)もやっている。能〈鞍馬天狗〉を出した時は花見の子方に地元の子供達に大勢出てもらった。もう二十歳にもなるという。それ以後私が忙しくてお稽古に行けなくて申し訳ない。今年は小田原から子供たちの舞囃子(研能会の長谷川君指導)の参加有り。元気な舞台だった。
まあ今年は暖かいところでお客様に能をゆっくり見ていただいたということで…。なごやかな交流会の後またバスで帰る。有難うございます、また来年。
都内に入って高速が工事渋滞。銕仙会について23時20分頃。今年は寒くなくて体力が奪われなかったのか、帰りのバスの中で比較的皆起きていて(お弁当も食べ)、何となく色々話が出来た。皆さん有難う。
遠い人はどうしたろう。私は装束も有ったので(明日もあるし)、もうタクシーでうちまで帰る。高速代(首都高、東名)込みで15,900円。いつもそういう時は個人の車を探すが、今日は日本交通、いい車、いい運転手さんだった。社長がお医者さんの出で健康管理がしっかりしている事など聞く。明日も京都へ日帰りと言うと「え、日曜日に仕事ですか?」 。
元気にがんばりましょう。 |
 |
 |
〔06/04/01〕わお!宝くじ二億四千六百万!あたったった…。春来る。 |
【045】 |
 |
|
 |
末娘(ソフト娘)の早稲田の入学式。初めてのストッキング。初めてのスーツ。初めてのパンプス。切り火を切って送り出す。歩き出したとたんに、「足痛ーい」。あとで運動靴持っていってやらなくちゃ。
 榊の花が満開。かわいいランプのような花が鈴なり。アケビの花が満開。ワインレッド、お日様に透かすととても美しい。浦島も咲いた。糸がタラリ。谷戸山公園のほうからホケキョも聞こえる。 榊の花が満開。かわいいランプのような花が鈴なり。アケビの花が満開。ワインレッド、お日様に透かすととても美しい。浦島も咲いた。糸がタラリ。谷戸山公園のほうからホケキョも聞こえる。
この間S君来たり二人でまた土筆と野蒜摘む。「朋有り遠方より来る、また楽しからずや」。
桜は満開にまだ少しか。駅からうちのほうへ曲がってあと小田急の線路に沿って桜の並木。明日は雨という予報。今日は花見が多いか。来週までもってくださいね。
かみさんとあとで出て、学生証の交付等で先に出た娘と12時に演劇博物館の前で待ち合わせ。ここは静かでよい。今度早稲田のつつじ能の時、演博所蔵の装束で使えるものがあれば使わせてもらうのに、また打ち合わせに来なければ。
歌右衛門の展示をやっていて見たいと思ったが、ソフトの仲間と五人(この前まで関東大会、選抜、インターハイと戦ってきた宿敵同士が今はもう本当に親しげ)でやってきて(足痛げ二・三人)すぐご飯ということになり、みんなで大隈通りへ。小上がりの空いていた「静」へ。ここは私が在学中に開店した店。当時はきれいでしゃれた店だった。おじさんおばさんも年季が入った。一人のとんかつ定食(650円)忘れて後に(しかしさすがにチームプレイの仲間だ。何とも言わずにみんな待ってる。声はでかい、ここは静)。みんなスカートで座るのは慣れない様子。「あぐらかきたい!」。
店を出たところで観世会の連中に発見される。新入生を一人連れている。
35年前の私。
私が始めて連れて行ってもらったのは地下鉄の駅の近くのラーメンの「メルシー」。今でもそこを通るとつい入りたくなる。モヤシそばの大盛り、もや大(今390円かな)。そこに連れて行ってくれた先輩が今仙台の東北大学にいて去年の〈望恨歌〉韓国公演の時、コーデネイトから通訳まで大変お世話になった成澤さん。学生時代は中国文学専攻。一噌幸政先生に笛も習っていて、ビニールパイプで作った能管をよく部室で吹いていた。
構内や入学式の会場に向う道は新入部員獲得のためのサークルの人たちで大変混雑。さすがに娘たちにはスポ−ツサークルの人が寄ってくる。アメリカンフットボールとか…。
新入生多く全学部を三回に分けて入学式の三回目。一時間以上前に入って前の方。開会まで時間がずいぶんあると思って謡をおぼえ始めたら、交響楽団と吹奏楽団のそれぞれの演奏。ミニコンサート。なかなかいいね。それと応援団、校歌「都の西北」とエールとコンバット。かっこいい!体がああ決まりたいもの。
白井克彦総長の挨拶。三つのLのお話。「Love」と「Low」と「Lavor」。学生部長さんからは個人情報をくれぐれも大事にという事のみ。
うちのかみさん、高校のソフトの応援では「フレーフレーおばさん」。これを見てからだったらもっとカッコよかったか。この前も娘と二人春の選抜の応援に佐賀の伊万里まで行ってきた(残念ながら雨で順延があり最後まで応援できなかった。そして結果は準決勝で敗れて三位)。
佐賀の白石というところがかみさんの実家。なかなか帰省できず久しぶりの父母・親戚のお見舞いにもなった。
大阪の娘からかみさんに葉書有り。「お弁当作り卒業ですか?」 いやまだまだ。
これとはこないだ長山禮三郎さんの会(独立40周年の記念会、おめでとうございました。呼んでいただいて有難うございました)で大阪へ行った時、久しぶりで会った。天満の天神さんの前、朝陽会館の隣の「豊」さん(かつて先代銕之亟師によく連れて行って頂いた。季節のものがとてもおいしい)にて。大倉源次郎氏、野村四郎氏らお顔を出される。この日、四郎先生は芸術院賞受賞の発表有り。しかしこの時は存じ上げなかったので、翌日大槻能楽堂にてお祝いを申し上げる。
豊さんへ行く前時間があったので清水のお墓参りへ。京阪の香里園駅から徒歩。久しぶりに伯父さん伯母さんにお目にかかる。デイサービスに通っているとのことであったが、お元気そうで何より。今度は娘も連れて伺います。
昨日は多田先生のところに久しぶりにお邪魔して今様能〈横浜三時空〉(横浜飛天双〇能)の打ち合わせ。少し本を書き換えられたのでこれを今度は私が節付する番。五月末を目途に。
先生はこのところリハビリについての法制が変わることに怒っているとおっしゃる。何でも180日しか保険医療が受けられなくなるとか。私の親戚でも今二人リハビリ真っ最中。どうなのだろう。
打ち合わせのあと、ちょうど先生の七十二歳の誕生日ということでバランタインの30年をいただく。日本放送協会放送文化賞の授賞式の写真を拝見、やっぱり蝶ネクタイ。重ねておめでとうございます。
日記このところ書けなくて、その間色々なことがあってまとめて書こうと思ったが、やっぱり時間なし、今日のところはあきらめよう。また…。
昨日が旧暦三月三日か。お雛様しまってないよ。四月三日までいいよ…。 |
 |
|
 |
|