|
|
 |
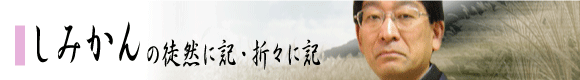 |
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
今日は午後1時より(のはずが、事務所で何かかんかしていて、実際には1時半ごろから)青山銕仙会での稽古日。後から場所を取ったものだから、3階楽屋の稽古場しか取れず、動く広さは無いので今日は謡の稽古に集中。まあ、この間、発表会が終わって新たなものを始めているのちょうどよかったかな。
しかし、型の稽古があれば、時々は立てるのだけれど、謡の稽古ということは、相手は変われど、こちらはつまりはずっと座りっぱなしで、終わったら、ウウ膝が・・・、袴もシワシワ・・・。
①阿漕=キリの仕舞の部分(録音)
:地獄で責められる様を表す仕舞だが、漁師が網を引く部分では、自分が網に追い込んだ小さな魚がとてつもなく大きくなって悪魚毒蛇となって・・・。その辺の型、きちんとイメージがつかめると面白いですよ。
②六浦=復習 次第ヨリ
今日新しいところは、 シテの呼掛けヨリ 中入マデ
:これは相模の国、金沢文庫・六浦の称名寺。例の渡辺淳一原作、黒木瞳主演の映画の中で、薪能のシーン(私が〈葵上〉を舞った)はここで舞台を組んで撮った。寒い日で今にも雨が降りそうで、映画も含めてあんまりいい印象はなかったな。ワキもツレも装束来て座っていたんだけれど、実際は全く映っていなくて、気の毒千番! いつかは普通に役者として映画に出たいものだが・・・。
③絵馬=復習 ワキ「いかに… ヨリ
今日 クセヨリ 神楽ノ前マデ
:シテが舞うのは「中之舞」で簡単そうだけど、これが天照大御神だからその位が…。シテの謡いの張りも尋常なことではないよ。
④盛久=ワキ「有難やこの御経を…ヨリ 物着マデ
:ここの地謡のところで盛久がお告げを得る。そこでふっと手に持ったお経を落としそうになる。その演技と、何でもなさそうなそのところの地謡が…。 この曲を響の会でやった時は、先代銕之丞先生がもう具合が悪くて結果稽古をしていただけなかったな。
⑤朝長=復習 ワキ次第ヨリ 初同マデ
:ここの地謡、漢語がその喪失感、悲しさを、寂しさを、寒さを引き立てる。あ、全曲録音しておくんでしたか、あらすみません、まだでした。御夫君を亡くされて早や一年経ちましたか。お元気になられてお稽古復帰、こちらも楽しみです。80歳を過ぎられたけれども、芯のある声で、本は見台に置かれても大体覚えて謡われる。またよろしくお願いいたします。
⑥笠之段=アシライ入りニテ
:この方はもう90歳を過ぎていらっしゃるが、最近囃子入りの謡をやりたいと、毎回自分で予習をしてきて、私が囃子のアシライを。先日の清門会では〈老松〉の舞囃子(舞は「眞之序之舞」!)を力強く舞われた。
⑦小塩=後シテヨリ トメマデ(録音のみ)
:今日は体調(咳が…)のため、録音のみにて。花の佳曲なり。しかし業平さんどんな美男子だったんだろうね。そしてお妃さまを奪っていく! その景色が本当に美しいものとしてみんなイメージしたんだろうね。
⑧実盛=シテノ語ヨリ トメマデ
:この前舞台でやったところ。語りから地謡一気にやるとずいぶん分量あるんだねえ。そうだ、前シテで謡っていたら、なんだか唾がたくさん出て困ったが、中入りで気が付いたらほっぺたの内側を噛んでいたんだ。アウチ!
*次は対極のような〈芭蕉〉を
⑨大原御幸=復習 法皇「実に有難き… ヨリ トメマデ
:この前の清門会ではこの法皇を謡った。青山で清門会をきちんとやるようになって初めての時に同じく〈大原御幸〉の素謡を番外で出して、シテが先代銕之丞、私は局の役だった。今日の稽古の中心、シテノ語りは内弟子の時に先代銕之丞師の桐朋の演劇科の卒業生の稽古であったので、その次にあった〈朝長〉の語りとともに耳に深く残っている。
*次は世阿弥の名曲〈鵺〉を
⑩田村=復習 初同ヨリ トメマデ
:ずっと札幌に転勤になっていて最近東京に帰り、これが復帰二度目の稽古。ちょうど京都の出身。熱心だったし、音感がいいので謡ってみて、基本は大丈夫、覚えていますよ! 少し感を少し取り戻せば。またやりましょう。
⑪養老=ワキ「実に有難き… ヨリ トメマデ
:少し変わった脇能だけれど、さっぱりしていい曲だよね。小書の時に緩急を著しくつけるけれど普通はそうでない。どうもこのところ他の曲でも常のものが小書風な演奏になっている事あって遺憾に感じることあり。
では次も強吟の稽古に面白い脇能にしましょう。*次は〈江野島〉を
⑫鞍馬天狗=復習 シテ名宣ヨリ
今日 初同ノ後ヨリ 「此方へ入らせ給へや マデ
:シテは鞍馬の大天狗になっているが、あくまで主人公は子方の牛若丸で、シテはそれを盛り上げる役と思わなくてはいけないな。初同「花咲かば告げんと言いし山里の使いは来たり馬に鞍(置け)」はいつもああそうだ、若き頼政の歌だなと思うところ。
⑬歌占=シテ「それ今度の所労を ヨリ 次第マデ
:この語りは、バナナのたたき売りのようなもの、緩急ありながら一気呵成にしゃべりたてる。本当と思わせる工夫が必要。一昨年か、私が国立でこれを舞ったとき、沖縄の一中健児の塔・資料室を見て帰ってインフルエンザに罹り、なかなかその熱が引かず、ようやく下がって間にはあったけれども、体に力が入らず、謡も出てくるのかどうか不安で、しかも普段直面のところ面を掛けてやることにしてあったので、なかなか苦しいことであった。
以上。定刻9時を5分ほど過ぎて終了。
こうして一日謡っていると、楽しいし、普段謡わない曲も謡い、これはこうかなとも思いつつ、声の出し方も実験し、実は自分の稽古になっている。しかもお月謝を頂戴しつつであり、まことにありがたいことなり。
私は稽古場はあまりなく、ここと会社の稽古一つと学生の稽古一か所。去年、沖縄と長崎の新作能を作るについては時間が少しでも欲しくて、国士舘の授業を谷本君に代わってもらったので、学校も集中講義の沖縄県立芸大だけになった。
しかし、この強制的に自分の稽古をさせていただく時間も貴重、もう少しそういう時間を持つべきかもしれない。お休みの方々もどうぞ、新しい方もどうぞ。まあ、じっくり稽古しましょう。
|
 |
|
 |
|