|
|
 |
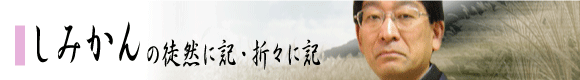 |
 |
 |
|
|
 |
 |
〔'10/05/17〕田んぼの水面に青い空 蔵王のてっぺんにまだ雪
 |
|
 |
|
 |
毎年になっている山形の東北芸術工科大学の薪能。〈葵上〉シテ観世銕之丞。私は主後見。池のなかの大きな能舞台。橋懸りが長く角度が急で、いつもにない工夫、演出が必要。今日は常の物着。この時、どう後見が被き(かずき)の唐織を持っているか、ただ隠せばいいということではない演出上大事なことあり。だが、それが今日のメンバーはわからない。遺憾なり。それでは本当の能は舞えないんだよ・・・。
いつもはカエルがゲーコ ゲーコだけれど、寒かったんだね、まだ鳴かず。途中の山形新幹線、峠でも新緑はきれいだけれど、未だ藤は咲かず。
今朝は、水道橋宝生能楽堂にて今度の谷本君の会、「煌の会」の申合せあり。さて、あとは本番。もうひと詰めを。しかし、〈道成寺〉を舞うということは大変なことだ。さて私も二回響の会でやったわけだが、自分ながらよくやったものだ。わお!
昨日、一昨日と能楽学会の大会が早稲田であり、全日程参加。この土日に仕事ないとは、幸か…。(土曜日は終わってから学生さんたちの稽古、そして新歓コンパ。5名の新人あり。頼もしい。頑張ってくれたまえ。例によって高田馬場駅頭ロータリーにて校歌・応援歌・エール・「千秋楽」あり。)
しかし、表先生の記念公演にもあったけれども、「観世寿夫さんがいたから私もここまでこれた」ということあり。逆に「戦後の能楽研究なくして、現在の能もなし!現在最先端の研究に参加していかなくては、あすの能は無い!」と言ってもいいのではないかな。
二日目は能面に関する論議があったが、もし室町の能面がその力として最も素晴らしいものだとするならば、それはその時代の能を作る力が最も大きかったからだろう。
私が銕仙会に入ったころは毎月一回銕仙会の主な方々が集まって、西野春雄氏を講師に世阿弥の伝書を読む会をやっていた。それが終わって私たちも若い世代で、表きよし氏を講師に世阿弥の伝書を読んでいた。申楽談義の半分くらいまで行って、なかなか集まれなくなってしまった。もう一度やりたいところだね。殊に金春禅竹を読んでいきたいね。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
2010年度能楽学会第9回大会プログラム
第1日 5月15日(土)13時より 於 早稲田大学小野記念講堂
◇ 能楽学会代表挨拶 天野文雄
◇ 大会会場校挨拶 竹本幹夫
◇ 研究発表
1浮遊する焦点―世阿弥「序破急」論の芸術論的特質 玉村 恭
2禅竹能楽論における「一露」「一水」再考 高橋悠介
◇ 恩賜賞・日本学士院賞受賞記念講演
「八人の先達と私」 表 章
第2日 5月16日(日)10時より 於 早稲田大学小野記念講堂
◇ 研究発表
1本間主馬(佐兵衛・俳号丹野)と伊勢 喜多真王
2近江井関の切型図 アダム・ゾーリンジャー
3彦根藩井伊家による能面購入の経緯―能面売買に関わるヒト・モノ・カネ―
米田真理
昼食・休憩
◇ 総会
◇ 大会企画
□ 第1部講演
1能面らしい能面の形成と伝承作家の問題 田邉三郎助
2面に刻まれた能の歴史 大谷節子
□ 第2部対談 司会 山中玲子
「演者と面」 観世銕之丞・山本東次郎
□第3部パネルディスカッション 司会 小林健二
田邉三郎助・大谷節子・観世銕之丞・山本東次郎
◇懇親会 於 早稲田大学大熊会館2階
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
本間主馬は宝生流の役者で大津・京都を拠点に伊勢でも活動したらしい。そして芭蕉と交わって俳諧もプロとして活動していたらしい。あるいは彦根藩をめぐる面の売り買いなど、能の周辺の経済活動を見るのも、大変面白い。借金のかたに面を出しておいて、金返しても、それ売っちゃうんだ! もしかしたら、教科書で習った日本の歴史観を変えるような、生き生きとした歴史が見えてくるかもしれない。私も、この何年か、新作能をやるについて、私の経済が立ち行かなくて、面装束を実は何点も手放している・・・。
組踊を作った玉城朝薫は一体どんな能を見たのだろうか。ずっと興味を持っているが、「見た。」とはどこにも書いてあるのに、何をいつ見たかは書いていない。さてこれはきちんとしなくては。
さっきの楽屋の弁当のおかずは、山形牛のローストビーフなり。帰りの電車の中で、一杯やりながらいただく。さて、そろそろ明日の稽古能・申し合わせの勉強もしなくては。あ、それから、午後は青山の稽古日だ。さあ、この前の続きどこまで行くのかな。申し訳ないけれど、稽古能の後、少し国立に申し合わせに行くことになったのでちょっと遅く始めます。よろしく!
|
 |
|
 |
|